2 MAMIYAの番犬
宗盛から連絡を受けた御殿は、端末片手に真剣な表情でやり取りをしていた。
「はい……はい――わかりました。後でそちらに向かいます。では後ほど――」
叶子の精密検査が終わったことを告げられ電話を切る。
背中のダメージが大きいのか、ベッドで休んでいた狐姫が
「叶子、どうだった?」
やや元気が削げ、かすれた感じの小声で聞いてくる。友の安否を思ってか、不安は隠せないようだ。
「大丈夫、心配ないわ」
「そうか……よかった」
胸を撫で下ろし、起こした上半身をふたたびベッドにあずけて眠りについた。
幸いにも叶子は軽い打撲だけで済み、他に異常は見つからなかった。瞬時に対応した狐姫のおかげである。
追伸として、宗盛は他用のために護衛をはずれる。指導者の代役として、愛宮邸ボディーガードが指名された。若くしてリーダーを務める頼れる人材と聞く。
華生も護衛にまわるとのこと。戦力は多いほうがいい。
何者かがMAMIYAの首に牙を当てている――御殿の予想よりも状況は悪化の一途をたどっているのは明白だった。
叶子は愛宮邸に戻り、現在は療養をとっている。
どこで、誰が、何を狙っているのか曖昧な状況下。見えぬ敵の手の上、
冷静になれ。ゆっくり深呼吸をしろ――御殿は深く呼吸を整えた。
想夜は朝早くに妖精界に帰った。今頃はフェアリーフォースとやらにいるのだろう。戦力が1名欠けているのは大きな損失だ。華生だけでも充分な戦力になる。が、令嬢用の番犬は多いほうがいい。
けれど愛宮邸ボディーガードのリーダーを任されている男が戦力についている。それは相当の実力の持ち主ということ。心強いことには違いない。
今回、狐姫のおかげで事なきを得たが、暴力祈祷師だけでは心もとない。と言われようが仕方がなかった。あってはならない事態が起こってしまったのだから。
(今は任務遂行だけを考えましょう……)
リーダーに同行することもあるだろう。今後のことを話し合うため、御殿は愛宮邸に向かうことにした。
ベッドで休んでいた狐姫が目を覚ましたので誘ってはみたものの、他用があるらしく、家に残してきた。
要件は聞いていない。お互いのプライベートには深く関らないことにしている。
愛宮邸の外壁にそって御殿が歩いている。
その横を一台のリムジンがゆっくりと追い越し、正門前で停車した。
車のドアが開き、中からワラワラと男女が降りて出てくる。
(……愛宮のボディーガードか)
部外者ではなかったので一安心。
御殿はリムジンに歩み寄ると、ちょうど車内から出てきたメガネをかけた青年と出くわした。
御殿より頭半個分突き出た長身の男――グレーのスーツとコートで身を包み、手には皮手袋をはめている。逆立てた銀髪の毛先は地獄の針山のように突き出ている。いっけん細身ではあるが胸板が厚く、ガタイもよい。御殿レベルの戦闘経験者なら「何かしらの格闘技をかじっている」と一発で分かる体格の男だった。不自然な脇の膨らみがあることから、銃を装備しているのは一目瞭然、それも左右に一丁ずつ。けれど銃を抜くことなどあるのだろうか? 体術だけで何人も息の根を止めてしまいそうな、他のボディーガード達とは別格のオーラを放っている。明らかに『やり手』だった。
そして御殿は見抜くのだ。この男が愛宮邸ボディーガードのリーダーだ、と
緊迫した状況下、口の中が乾いた御殿はゴクリと生唾を飲み、男に近づいた。
「はじめまして。わたくしは――」
「知っている」
御殿の紹介を最後まで聞かず、男は機械のような感情の無い声で口を開いた。
めがねフレームの隙間から見える鋭く冷たい眼差しに息を呑む御殿。
男が口を開いた。
「俺は小安。護衛のリーダーを任されている。契約期間だけ、貴様も俺の部下ということになる」
(この人、元軍人だ)
御殿は一瞬で察した。
愛宮邸には傭兵あがりのボディーガードが多く在籍している。戦場をくぐってきているかどうかなど、目や俊敏な身のこなしを見ればわかること。筋肉の付き方ひとつで、その者がどのような生活を送ってきたのかは一目瞭然だ。
男は車のドアを閉め、御殿を残して愛宮邸に向かう。
その光景を黙って見つめる御殿。
すれ違う小安。
御殿の真横で足を止め、メガネをくいっと上げ、見下ろすように睨みつけた。その後、すぐに御殿から視線をはずして正面を向く。
「とんだ失態だったな、咲羅真御殿」
御殿の体が固まった。目を伏せるのは己の失態を認めている証拠である。
互いに視線を合わせることなく、別々の方向を睨みながら会話を進めた。
「申し訳……ございません」
己の戦力の至らなさに御殿は下唇をかみしめた。
そこへ小安が容赦なく追い討ちをかけてくる。
「叶子お嬢様がご無事だったから貴様を生かしているようなものだ。でなければ、今ここで貴様を蜂の巣にしている」
小安は御殿のジャケットの胸倉を掴んで顔を引き寄せた。女子供とて容赦はない。
生粋の男の腕力を前に、スレンダーな御殿の体は簡単に吸い寄せられてしまう。
MAMIYAに仕える野獣同士、まっすぐな視線で見つめあう。
1センチ――あと1センチ近かったら頭突きをかまされていたところだ。互いの息がかかる、それほどの近距離から睨んでくるから威圧感がハンパない。叶子を危険に晒されたのだから、それだけ怒り心頭なのだ。
「いいか、よく聞け咲羅真御殿。MAMIYAで護衛をするということは、死んでも主を守れということだ。牙になれということだ。盾になれということだ。言っている意味が分かるか?」
「……承知しております」
小安は御殿の体を睨みつける。
「防弾コルセットをつけているということは自分が可愛いということだ。撃たれた時の痛みから逃げている証拠だ。違うか?」
「……違いありません」
「ジャケットの左胸にハートプレートも仕込んでいるな。死ぬのが怖い証拠だ。違うか?」
「……違いありません」
「撃つ者は撃たれる覚悟が必要だ。撃った弾丸はいつか自分に返ってくる。重装備は心強いだろうが動きを鈍らせる。のろまな番犬はクソの役にも立たん。悔しければ相方を見習うんだな」
「……承知いたしました」
と、そこへ庭の手入れをしていた菫が割り込む。正門でのやり取りを聞き、何事かと駆けつけてきたのだ。
「ストップ、ストーーーップ!」
慌てて細身を小安と御殿の間に捻り込む。
「小安さん、大人気ないでしょ。叶子ちゃん無事だったんだから良かったじゃない。 ……ね?」
ガキ大将を諭すように菫が小安に笑顔を作ると、呪縛が解けたように小安の拳から力が抜けた。
小安がふたたび御殿と視線を合わせる。
「今回は菫さんと貴様の相方に免じて許してやる。次はない、ゆめゆめ忘れるな……」
小安は静かに話しを終えると、御殿の体を突き飛ばし屋敷の中へ入っていった。
その後を菫が追うように消えてゆく――御殿に向けた笑顔は慰めのつもりだ。「そんなに力むことなんてない。もっと肩の力を抜きなさい」。そう語っていた。
御殿は黙ってうつむくだけだった。ひとり壁にもたれ、つまらなさそうに空を見上げる。
雲の流れを目で追いつつ、少し昔のことを思い出していた。帰国する前、傭兵紛いの御殿が戦場で何度も味わった苦い思い出。失敗すれば死、生き残ったとしても暴魔戦の恐怖から心身をやられた者達。彼らの末路が頭にこびりついてはなれない。御殿自身、悪夢で目が覚めることは珍しくない。
日本に戻ってきてから平和ボケでもしてしまったのだろうか。学校生活という「一見、安全そうに見える環境」が御殿を戦場の野獣からペットショップの子犬に変えてしまったのか。
――それとも、相方の戦力に甘えているのだろうか?
自分はMAMIYAの番犬として、自覚が欠けているのだろうか――小安に圧倒された。MAMIYAのために命を差し出す覚悟を持った番犬の眼光。あれを前にしたら誰だって尻込みするだろう。
自分には覚悟がたりないのか――御殿の葛藤は尽きないままだった。
帰宅した御殿は自室へと向かう。
家には誰もいない。外出した狐姫はまだ帰ってきていないようだ。
ジャケットを脱ぎ捨て、防弾コルセットをはずす。腰まわりが若干軽くなった。暖かくなるとむれるので好きじゃない。
ついでキュロットとストッキングも脱いでブラウスのみの姿となり、ベットにゴロンを身を預けた。
装備を外したからだろう、身軽になって開放感に包まれる。まるで拘束具から開放された気分。
小安の言葉が胸に刺さる。防弾コルセットもハートプレートも命を守る必需品だ。が、それに頼りっきりなのはどうかと自分でも感じる。後生大事に持っているお守りじゃあるまいし。
「……ふう」
ベッドに体が沈む。
柔らかい布団に包まれていると、誰かに寄りかかっているようで楽チンだ。
いや、誰かに身を預けているようで安心する。それが本音だ。
枕に半分顔を沈めては、つまらなさそうに目の前のシーツを無意味に見つめる。
「……」
静まり返った家の中は違和感がある。
日頃、狐姫がキャンキャン騒いでくれるおかげで、余計なことを考えずに済んでいたのだろう。こうして1人でいると、いらんことばかりを考えてしまう。
ネガディブに浸るのは趣味じゃない。けれど、最悪の事態を考えるほど臆病じゃなければ生き残れない。軍人、傭兵、皆、警戒心でビクビクしているのが本心だ。精神が半分イカれて、笑いながら銃器を吠えさせて地雷原を突っ走る者もいる。珍しいことじゃない。狂っていること自体が快感なのだ。そうでもしなきゃ恐怖は消えない。アドレナリンにすがりつくのが日常だ。
撃つ者は撃たれる覚悟が必要だ――さきほど小安に言われたことが御殿の脳裏によぎる。戦場でうんざりするほど聞かされた言葉。決して忘れていたわけではない。おかしなことに自分は死なないという変な思い込みが芽生えていたのだ。狐姫の戦力に甘えている心理からきているものだと思った。
「いつからこんな腑抜けになってしまったんだろう……」
攻撃は最大の防御。
戦え。
戦え。
死にたくなければ戦え。
御殿は少しの間、目を閉じた。
――微かな物音で目を覚ます。
少し眠ってしまったようだ。時刻は夜8時を回っていた。
御殿は目をこすりながら身を起こす。まどろみの中、台所から物音がすることに気づいてベッドからおりた。
きっと台所にいるのは狐姫だろう――寝癖、寝ぼけ眼の御殿は台所へ向かった。
「狐姫、帰ってたの?」
「おう御殿、起きたか。ハラ減ってね? 今メシ作ってるから待ってろよ、ファイヤー!」
ボウッ! コンロから鍋に移った炎が雄たけびをあげる。
狐姫がエプロン姿でせっせと晩メシの支度をしていた。無駄な火力で何を作ってくれるのやら……ちょっと楽しみ。
「わたしも手伝う」
御殿が袖をまくり手を出そうとするも、
「いいよ、任せとけって」
狐姫はそう言って1人で準備を進めてゆく。
「そう? じゃあ狐姫の腕を信じましょう」
「おう、そうしろそうしろ」
御殿はテーブルでのんびりすることにした。
こんな感じでいつも甘えていることが許されるのか。と、自問自答しては叶子襲撃のことを思い出してしまう。
この先、狐姫に頼り過ぎると狐姫の身が持たないかもしれない。
叶子にも、MAMIYAの件が解決するまで安全な場所に留まってもらうほうが得策なのではないか?
失敗が弱気を引き寄せることは誰しもある。
――普段はテレビを見ない御殿だが、持て余す空間に耐えられなくなってリモコンに手を伸ばした。
その時だ、寝室に置いてきた端末が鳴っていることに気づく。
(電話? 誰からだろう?)
御殿は寝室に戻り電話を手にする。
「はい、咲羅真です」
電話の向こうから相変わらずの元気な声が聞こえてくる。想夜だ。
『御殿センパイ、今からお邪魔してもいいですか?』
「今から? 別に構わないけど……」
突然の申し出に驚いたが、夕食も近いことだし一緒に食事と洒落込むのもいいだろう。フェアリーフォースとの進捗状況も聞きたいところだった。
御殿は話しながらリビングに戻った。
「何時に来れそう?」
『もう来てます』
「?」
ベランダから物音がする。誰かがいるようだ。
御殿がカーテンを開けると、窓の向こうでは想夜がホッペをベタリと張り付かせているではないか。
ガラリ。窓を開けて想夜を中へ招く。
「……お早いお着きで」
「えへへ。飛んできちゃいました」
便利な羽ですね。
「お邪魔しま~す♪」
台所の狐姫を見るやいなや、想夜がフンスーと息を荒くさせた。
「あ! 狐姫ちゃん、耳に指が入りそう。エプロンかわいい……尻尾さわらせて♪」
想夜がすかさず狐姫の背にすがりつく。
「おまえ、言葉のつなげ方おかしいだろ。言語能力なんとかしろよ。あと、それ以上近づいたら串刺しにするからな」
笑顔の想夜に向かって、説教モードの狐姫が菜箸をカチカチさせて威嚇する。
「えー、先っちょだけならいいって、このあいだ約束したじゃん」
「してねーよ。そして、せめて玄関から入って来い」
「着地はベランダのほうが楽なんだよ?」
「おまえはスズメかっ」
飛べない人にはわからない感覚です。
想夜の姿を見た御殿が驚きを見せた。
「どうしたの? こんなに汚れて」
ボロ雑巾のような格好。擦り傷切り傷の多いこと、まるで全身を爪で引っかかれたかのよう。
見かねた御殿が頬の汚れを拭き取る。
想夜は照れながら、空の弁当箱を差し出した。
「これ、ごちそうさまでした」
御殿は中身が綺麗になっているのを確認すると、想夜の頭をポンポンとなでた。
「全部食べてくれたのね。えらいえらい」
「……えへへ。とっても美味しかったです」
――本当は美味しくなかった。
とは言えなかった。
弁当の中身をぶちまけて、それを拾っては弁当箱に戻したのだから。
人間界に戻ってきた後、弁当を口いっぱいに詰め込んだが、味なんか分からなかった。
その辺の土をつかんで口に放り込んでいるのと何ら変わらない感覚だった。
せっかく自分のために作ってくれたお弁当を味わうことが出来ないでいる。しかも美味しいだなんて嘘をつかなくてはならない。そのことが、ひどく想夜に罪悪感を募らせた。
御殿は想夜の曇る表情に違和感を感じるも、あえて追求することなく弁当箱を受け取る。
「傷の手当てをするから、先にシャワーあびてきなさい。夕食、食べてくでしょ?」
「はい、ありがとうございます♪」
弾むように言う、いつもの素直な態度。その後、想夜は足を止め、ゆっくり振り返った。
「……シャワー浴びたら、お2人に話があります――」
そういい残し、バスルームの扉をしめた。
暗い表情の想夜が気になった。御殿と狐姫は無表情で互いの顔を見ていた。
食卓。御殿が想夜にお茶碗を差し出す。
「はい、想夜の分ね」
「わーい♪ ありがとうございます!」
席についた想夜は御殿から山盛りごはんを受け取った。お弁当があんなことになってしまったので、チョーお腹ペコペコ。
夕食は鮭の塩焼き、浅漬け、お味噌汁、とシンプルかつ鉄板メニュー。
「いただきまっす」
あったかいお茶碗から白い湯気。守られているようで、なんだかホッとする。そんな安心感もあってか、いっそう箸がすすむ。
想夜は鮭の赤身を白米の上にのせると、それを一口。
「ん~、おいひー!」
ホクホクとした甘い白米に鮭の塩っけがまざりあい、想夜の箸を煽ってくる。
ポリッ、ポリッ、ポリッ。
歯ごたえのある食感、白菜とナスの浅漬け。これも箸がすすむ。しょっぱいものが想夜に語ってくるのだ。「白米と一緒にいたい」と。
食材の声を耳にしては、白菜でゴハンを包み込み、それを口に運ぶ想夜。
野暮用だったが、けっこうな移動距離だったため、疲労もたまっていた。そんなところへの塩分補給。体が喜ばないワケがない。
狐姫が想夜に語る。
「鮭はな、皮が一番ウマイんだぜ?」
「皮? あたしいつも捨てちゃう」
「おまえ全っ然わかってないね。全国の漁師さんに土下座して詫びろよ」
狐姫は残った鮭の皮に左手をそえ、それを箸で細かくちぎってゴハンの上にのせた。指についた背油をチュパッチュパッとワイルドに舐めとり、ゴハンに急須のお茶をぶっかける。
「鮭の皮にだけ塩を多めにかけておいたんだ。油がのってるし、しょっぱさがまたいいんだ」
と、狐姫は茶碗をあおってゴハンをかき込んだ。
想夜も見よう見マネで鮭の皮を指と箸でちぎってはゴハンにのせ、その上からお茶をぶっかけた。
塩がきいた鮭の皮のお茶漬け。
「フー、フー」
想夜は箸ですくって一口食べてみる。
「あ、ホントだっ、皮の部分だけ塩が多くのってる」
「お茶漬けってのはチマチマ食べるもんじゃねーんだよ」
と、狐姫は茶碗を口につけて煽り、箸でサラサラと流し込んだ。
想夜も習って、お茶漬けを一気にかき込んだ。一息入れ、よく噛み、浅漬けをお供に、ふたたびかき込む。
おいしい。今度は本当。本当においしい。
好きな人たちと、楽しい空間で食事をする――それが最高の調味料だということを、想夜は知っている。
「いちいち美味しいね、狐姫ちゃん」
「いちいち日本語おかしいな、おまえ」
ポリッポリッ。2人して浅漬けの音を鳴らしては茶碗を煽る。
なかよく食事をする手前、想夜に笑顔が戻ったことを喜ぶ御殿。ふと、先ほどの事を思い出す。
「そういえば狐姫、さっき火柱あげてなかった?」
おうよ。ファイヤー、とか言ってたぜ。
「ああ、アレ失敗な」
「失敗? 一体なにを作ってたの?」
「美食倶楽部、至極のメニュー。余った食材は全て狐姫ちゃんサマがいただきました」
ごっつあんです、どすこい。と、両手をあわせて会釈する。
「ふふ、しょうもない」
御殿、慎みある笑い。とはいえ料理に対する取り組みは誉めてあげたい。
御殿は想夜の口元についたご飯粒を指摘しながら聞いた。
「――で、フェアリーフォースで何か収穫はあった?」
「え、あ、はい……」
想夜は改まった感じで箸を置いた。
想夜はフェアリーフォース本部で起こったことを、御殿と狐姫に告げた。
「ヒュー、かっこいーな、おまえ」
「政府に挑戦するなんて、なかなかできないわよ。想夜やるじゃない」
「えへへ。ほんとは少し怖かったです」
想夜は紅茶がそそがれたカップに口をつける。お弁当のことを口にしかけたが、気を悪くさせてしまうと思い、閉口した。
想夜はフェアリーフォースでの収穫、それから廃墟での出来事を打ち明けると同時に、先ほど華生から渡されたカードキーと携帯に残した陣の写真を御殿に差し出した。
「――これは?」
「シュベスタのカードキーです。案内してくれた華生さんが赤帽子から奪ったものです。写真に写っているのが例の陣です」
吸集の儀式ではない別のものだ。
「赤帽子の群れとシュベスタ、か。あまり穏やかな話じゃなさそうね」
「はい、攻撃パターンも独特です。弱っているあたし達にハイエナのように群がってきました。残忍な性格の妖精たちでした。きほん、あたし達妖精は友好的な種族なんです。赤帽子も華生さんのように心優しい人もいますが、そうでない人も多いです」
「なぜそんな連中が人間界で群れを成して行動してるの?」
「理由は分かりませんが、別館の中に陣が施されてました。中庭の隠し下水路を通って別の建物に行くことができたんです」
「クソ、隠し扉か。全然気づかなかったぜ! きっとレアアイテムの宝庫だぜ」
ゲームか何かと勘違いしているようだ。
御殿は構わずに話を進める。
「――で、陣から赤帽子が溢れてきた、と?」
「はい。最初はローブをまとった術者が数人、召還されてきました。その後、ローブに呼ばれるように赤帽子たちが次々に――」
想夜の説明を聞く限り、赤帽子を呼び出したのはローブをまとった術者だと御殿は察する。
「となると、このままにしておけば術者が召還されるたびに赤帽子を呼び出してきそうね」
「妖精を呼び出す術式だったら、あたしや華生さんでも解読できるんですが、さっき見た陣は読めませんでした」
妖精界と魔界は陣言語が違う。
陣言語――陣を描くときに使用される言語。人間界で使用されているプログラム言語のようなもの。妖精言語、魔言語がある。エクソシストは魔言語が読めるものが多数存在しており、御殿と狐姫もそれにあたる。
ションボリと肩を落とす想夜。
「で、わたし達にその魔言語を読んで欲しいってことね」
コクリと想夜が頷いたあと、赤帽子のほとんどは強制帰界させた旨を伝え、御殿に知恵を求めた。
「そうね。写真を見るかぎりだと悪魔召還のようだけど、もっとよく調べたいかな」
一刻を争うかもしれない。
高度な芸当
想夜は御殿と狐姫を連れ、ふたたび元MAMIYA研究所の中へと侵入した。
これだけ頭数があると心強い。ましてや朝ということもあり、研究所内は明るく、遠くまで見通せることから安心感がある。
想夜はエクソシスト2人を問題の部屋に案内する。
「こっちです」
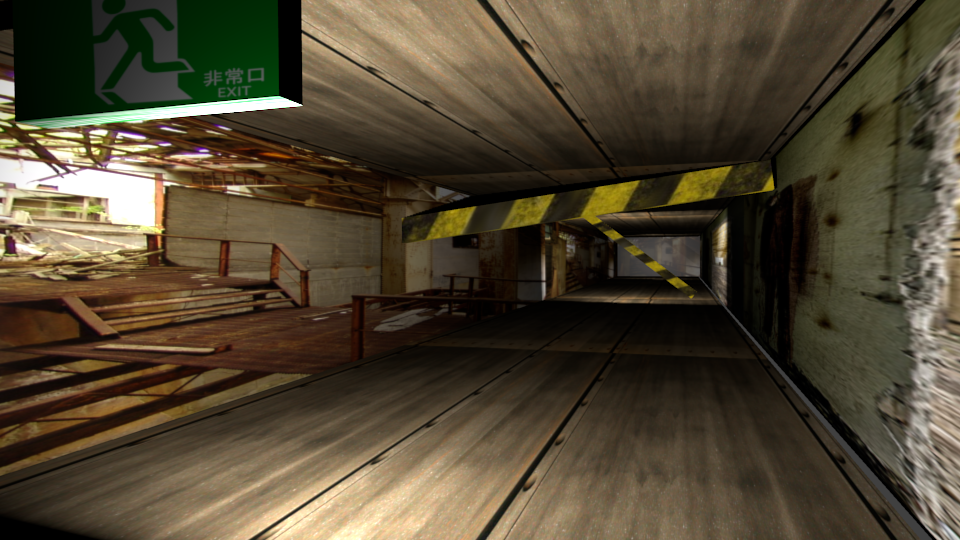
中庭は、昨晩の戦のあとが生々しく残っていた。
「足元気を付けて下さい」
想夜が先頭を歩き、血で染まった雑草をかき分けながら水路を抜けて別館へ移動。
やがて目的地にたどりつく。
あたりはシンと静まり返っており、物音一つしない。人の気配もなく、逃がした赤帽子が襲ってくる感じもしなかった。
御殿はライトをつけ、壁や床が切り刻まれている光景に異様さを感じた。
ボロボロにはがれた壁、チェーンソーか何かで削り取ったような爪痕、先ほどまで暴れていた形跡が残っていた。
「この傷、赤帽子の攻撃?」
「はい」
「派手に殺りあったみたいね」
「はい。バランサー権限で50人近く強制帰界させました。華生さんの協力の
想夜1人では手がつけられない戦闘だった。強い味方がついたのだ、と想夜は誇りに思った。
想夜は御殿と狐姫を一室に招き入れた。
「この陣です。あたし達妖精には分からない術式。でもエクソシストなら分かると思うんです」
御殿は床一面に書かれた陣に目を向けて難しそうな顔を作っている。
狐姫は陣の前に座り込み、アゴに手を添えて考える。迷……いや、名探偵狐姫サマの登場でい!
「見た感じ、一般的な降魔の儀式みたいだけど」
御殿がスタスタと奥へ歩いてゆく。
想夜がわからないのも無理はない。妖精たちは魔族との関りを一切持たないのだから、魔族召喚の術式など知る必要もないのだ。
狐姫が口を開く。
「悪魔召喚に使用する陣であることは確かだ。ここに書かれている関数を見ろ。魔族を呼び出すように書いてある」
そう言って、陣の一部を指差す。
関数とはプログラムコードの中で頻繁に出てくる公式。特定の数字などを関数にセットすると、内部に書かれた式に
御殿と狐姫はプログラマーがソースコードを読み解くように、陣をスラスラと解読していった。
「――狐姫、ちょっと来て」
部屋の隅、少し離れたところから御殿が呼んでいる。
「んーだよ、うっせーな巨乳」
よっこらしょ、狐姫が腰をあげて御殿のほうに歩いてゆく。すごく面倒くさそうにしてるあたり、陣を呼んでるところを邪魔されたくなかったのだろう。陣の解読は人間も妖精も神経を使う。想夜だってそう、解読中に横っ腹を突かれたら、「あーもー! ちょっと待ってて!」と、ヒスを起こすかもしれない。集中しているところを邪魔されたくないのは万国共通だ。
「狐姫、ここ見て」
御殿が陣の外れにある文字列を指差す。規則正しい六方星と円の隅に、何やらちょこちょこと書き込まれている。
狐姫は文字を眺めながら首をかしげた。
「なんだコレ? 見たことないコードだな」
一部分だけが特殊な書き方をしていた。
御殿が見た感じだと、魔族を召還した瞬間に別の関数が呼び出される仕組みのようだ。とはいえ、どこか妖精言語と同じ箇所がある。
御殿が部屋の隅っこのほうから想夜を呼ぶ。
「想夜、これは吸集の儀式とは違うの?」
指摘された文字列を覗き込んでは、想夜は目を丸くして声を上げる。
「あ、これ妖精界の文字です!」
一同ぶったまげた。なんと悪魔召還のコードの中に、妖精界で使用するコードが混ざっていたのだ。
「――ど、どういうことなんですか?」
不安そうな表情を浮かべる想夜の手前、御殿と狐姫は悪魔召還の陣の解説を始めた。
「まず、この陣の意味なんだけど、これは悪魔召還の陣で間違いないわ。問題なのはこの部分――」
陣の隅っこのほうを想夜が覗き込むと、狐姫が説明に加わる。
「悪魔召還の陣と、おまえらが使っている妖精言語が上手い具合に結合されているんだ。日本語の中に英語が混っているのに、一ヶ国語の文章として成立しているってこと。簡単に訳すと『悪魔召還時に妖精を添付しろ』ってことな」
狐姫の言うとおり、降魔の儀式に別の術式が呼び出されていた。
それを知った想夜は息を呑んだ。
「つまり……赤帽子たちは魔界からやってきた、ということ?」
「可能性大だな」
「魔族が妖精を……運んでるってことですか?」
御殿は黙ってうなずいた。
想夜はもう耳を疑がうこともできなくなっていた。視界がぐるんぐるん回って、後は何も聞こえない――そんな奇妙な感覚。ハンマーで頭を殴られた後の感覚、とでもいえばいいのだろうか。
確信的である。想夜はその場にひざまずく。
なんということだろう。赤帽子は妖精界から来たのではない。いちど魔界を通り、魔界から人間界に入界する方法をとっていたのだ。
『魔界は妖精界と手を組んだ――』。
想夜の脳裏、MAMIYA研究所で暴魔が言ったとされる言葉が頭で暴れる。「それが真実だ」と。
「想夜、あなたの気持ちを察してあげたいけど……魔界と妖精界が手を組んだのは事実みたいね」
想夜は呆然とたちつくす。怒りの矛先をどこへ向ければいいのか分からない。壁に向けて拳を叩きつければスッキリするのか? 足元に転がる石ころを蹴飛ばせば気持ちは晴れるか? どちらも意味のない行為だ。
「いったい誰が……誰がこんなことを」
ポツリ、つぶやき、
「う……ぐっ」
悔し涙でこらえた。
誰がこんなことを――答えは明白だ。
――フェアリーフォース。
出来すぎた召還の儀式。人間界でこんな荒唐無稽な芸ができるのは政府だけだ。
想夜は地面の砂を力まかせに握る。
握り締めた拳が痛いのではない、胸が締め付けられる感じがして痛いのだ。とたんに涙が瞳を覆い、喉の奥が痛くなり、妖精界の裏切り行為を前に、想夜はただ愕然とするだけだった。
「想夜……学校へ行きましょう」
御殿は陣を足でかき消した後、想夜の震える肩にそっと手を置いた。
想夜は腕で乱暴に涙を拭い、コクリ――ただ無言でうなずいた。
パーティー
パーティー当日。
つい先ほどの出来事。御殿は護衛のためにパーティー会場にいた。不審者がいないか周囲に目を配り、テーブルに並べられたフォークやナイフも一本一本チェックする。武器になるものは全て把握しておかねばならない。皿やシャンパンのグラス、ナプキンですら武器になりうるのだから気が抜けない。
テーブルの上に所狭しと並べられたオードブルを見る――食べる者のことを考えて作ったのだろう、おもてなしの心が行き届いた盛り付け方だ。シェフの人柄が想像できる。どんな人なのだろう、一度拝見してみたいものだ。
料理を運ぶ従業員の中には、華生の姿も見受けられた。額に汗、淡々と仕事をこなしているように見えるが、いつ誰が襲ってくるかわからないもんだから、内心、気が気ではないだろう。先ほどまで叶子の着替えを手伝っていたようだが、叶子の様子はどうだろうか?
御殿はインカムに語りかけた。
「狐姫、そちらの状況を教えて――」
イヤホンから狐姫の声が聞こえてくる――。
『異常なし。叶子の着替えも済んだ。これからそっちへ向かう。叶子のパンツの色教えようか?』
にしし、と笑う狐姫のすぐそば、『是非ともやめてね』と、叶子のにこやかで冷たい声。
「……了解、そのまま護衛を続けてちょうだい」
『おい御殿、無視すんなコラ!』
ブツン。
御殿はインカムを切った。
「――ふう、あっちは問題なさそうね」
奇襲を受けた叶子だが、容態に問題はなかった。翌日には登校できるほどに回復し、今ではパーティーにも出席できる。
不審な人物はいないか、御殿は何度も目を光らせは会場全体を見渡した。
時間が経つにつれ、出席者も増えてきた。
メディアに出演している人物がいる。
政治家の顔もめずらしくない。先日、愛宮邸で行われた全社総会に出席していた者も数多く目に付いた。
にこやかにしている者の中には生ゴミに群がる害虫の匂いを発するものもいる。腹の黒さは匂いで分かる。
「狐姫の嗅覚がうつったのかしら?」
とはいえ、皆、味気のない談笑にふけっている。いたって普通のパーティーと思っているようだ。一部の出席者を除いて。
そんな中、ある男が御殿に近づいてきた。
「ほお、よくもまあ、ここまで育ったものだな」
御殿よりもやや長身。ピクリとも笑わない強面には歳相応のシワが刻まれ、短めの髪を整髪料で整え、白髪交じり。全体にほどよい脂肪が備わっており、中年太りのそれとは違う。スリムでもなく太ってもいなく、医者から「少し油ものを控えましょう」と言われるレベルの体型。ほどよいムスクを匂わせており、「おっさん、おじさん」とも違う、ナイスミドルといったところか。
(確か厚生省の男。名前は……鴨原稔。MAMIYA研究所元副所長)
御殿の手前、鴨原は御殿の足元から顔まで、舐めるように視線を送ってくる。ポケットに両手をつっこみ、ふてぶてしい態度。
若干皮肉めいたように顔を歪ませ、「フンッ」と、ほくそ笑んでは去っていった。
また変なのが来た、と思った。あの男もひとクセありそうだ――御殿はかまわず時計に目をやる。
「18時29分、そろそろね――」
カリキュラムは以下の通り。
18:30 挨拶
18:35 総会 格企業 今後の施策説明、プレゼンテーション
19:00 パーティー開始
21:00 パーティー終了
沙々良の2次会は第3女子寮だろう。今ごろ想夜が身震いしているハズだ。
そんなことを考え、御殿がクスリと笑う。
肝心の想夜の姿がない。女の子なので支度に時間がかかっているのだろう。
とはいえ遅すぎる。一体なにをしているのやら。
(広い屋敷なので迷子になっているとか? ひょっとしたらメイドと間違えられて働かされているのかも? 可能性はゼロじゃないわね)
愛宮邸ボディーガードが各自ポジションにつく。
御殿は2階のパーティー会場入り口付近に配置された。
ふと視線を感じ、そちらの方向に目をやると、ある女性と目が合った。研究所主任の水無月彩乃だ。
御殿の視線に気づき、微笑んでは遠慮がちに手を振ってきた。初めて会った日の微笑み、お日様のような暖かい笑み。どこか寂しげな笑み。
彩乃の隣に沙々良と詩織も出席していた。両者とも目線がステージへ向かっており、御殿の存在には気づいてない。気づいたとしても護衛任務とは思わないだろう。きっと一学生としての参加と見られてる。とはいえ、黒装束はドレスに見えるのか?
御殿と彩乃のアイコンタクト――御殿は安らぎを覚えながらも、勤務中なので冷静をよそおって軽く会釈する程度にとどめる。それに妙に慣れ慣れしい感じもする。ほとんど面識がないどころか、数える程度の言葉しか交わしてない。おまけに想夜を襲った容疑者。思いっきり要注意人物である。
きっと彩乃は自分のことを無愛想に感じているだろう。そう考えながらも、御殿は背筋を伸ばして周囲に気を配る。どう思われようが仕事は仕事だ。
御殿の険しい態度に、彩乃の笑みが半ば諦め顔になる。
なんというのか、授業参観に来た母親が頑張っている子供を遠くから応援しているような、勉強の邪魔をしてはいけないので声をかけたくてもかけられない、そんなもどかしさを見せる笑みだった。
なにより御殿の獣のように鋭い目が近寄り難い雰囲気を出している。神経が張り詰めている人間は人を遠ざけるものだ。近づくなよオーラ、声かけんじゃねーよオーラ。言い方は様々だ。
18:30 挨拶
挨拶が始まった。一番手は宗盛からだ。
ガコ……
「あーあー。マイクテス、マイクテス――」
お約束のマイクテスト。会場内に鈍い音響。それで会場内が一気に静まる。
場内の照明がステージに絞られ、スピーチが始まった。
「会場のみなさま、本日はお忙しい中、お集まりいただき――」
流暢な口調で幕が上がり、プログラムが着々と進んでゆく。
彩乃のプレゼンもあった。御殿にはさっぱり分からない内容。英語とドイツ語を使い分けたり、専門用語の連発。本当に縁の無い人なのだと心から思った。
エリート街道まっしぐらの彩乃への嫉妬かもしれない。彩乃を見ていると何だかイラついてくる。胸の奥を引っかきまわされている感じがして、あまりいい気分になれない。ホワイトカラーとブルーカラーの差と言う奴か。体力勝負の暴力祈祷師はブルー側だ。マイク片手に呑気に喋る姿が癪にさわる。
生物、遺伝子工学、医療、サイバー、バイオ何とか――小難しいったらありゃしない。叶子は理系に進むらしいが、自分には一生縁の無い世界だと自覚する御殿。
19:00 パーティー開始
企業の小難しい説明も終わり、時刻は19時を回った――パーティー開始である。
食事をつまむ者。グラスを傾け談笑する者。各々がこの時間を楽しんでいた。
他の者はスタンバイできているだろうか? 叶子のことが気になった御殿は、ふたたびインカムに囁いた。
「狐姫、聞こえる?」
するとどうだろう、聞こえてきたのはノイズ、その後に叶子の声。
『ザザッ……る? ザッ……聞こえる? 御殿さん!?』
どうしたというのか、慌てている。何かが起ったらしい。
「こちら咲羅真。叶子さん? どうしました?」
『――られたわ!』
耳に入ってきた内容は……悪い知らせだった。
御殿の顔が見る見る青ざめてゆく。冷静になれ。我に返り呼吸を整えた。感情に振り回されていたら仕事は務まらない。
「……もう一度、お願いします」
叶子の焦る声がインカムに響いた。
『狐姫さんがやられたわ!』
そういい残し、インカムのスイッチは切れた。
御殿はその場に立ち尽くす。
「狐姫が、やられた?」
信じ難い。
一体なにが起ったというのだろう? なんの冗談なのだろう? 御殿の思考が目まぐるしく動く。
状況を確認したかった御殿は、近くにいた護衛の女に配置をズラしてもらうよう頼み、自分の配置エリアをカバーしてもらう。
緊急事態なら止むを得ない、と承諾してくれる柔軟な頭の持ち主でよかった。
奇襲があったことを護衛各自にインカムで通達すると、会場内にいるボディーガードの目つきが一斉に変わり、とたんに空気が張り詰めた。各々、出席者に感づかれないよう連携をとって動き出した。
御殿はパーティー会場から出ると、2階へと続く階段を駆け上がっていった。
廊下を走り、叶子の部屋の前にたどり着くと、扉が少し開いているではないか。
――まさか、叶子までやられたのでは?
最悪の事態を頭から振り払い、御殿は扉をノック。返事を待たずに部屋に飛び込んだ。
おめかし想夜
17:00
パーティー当日。
召還の件でのショックを隠しきれず、ただただ落ち込む想夜だったが、御殿がいっぱい頭をなでてくれたおかげで、少しずつ元気を取り戻していた。それにバランサーとしてやるべきことがある以上、立ち止まってなどいられない。
気を利かせてくれた狐姫にも笑わされた。
狐姫の冗談がおかしくておかしくて、腹がよじれそうだった。ほとんど御殿の恥ずかしいネタだったけれど、想夜の流す涙を笑い涙に変えてしまう狐姫のことを魔法使いだと思った。
赤帽子戦で受けた無数の傷が痛むけど、妖精界から持ってきた特効薬のおかげで傷も回復し、今では無理な動きをしても問題なさそう。
叶子の容態も問題がなかったので一安心。無事、パーティーにも出席ができると知った想夜は、いつもの笑顔に戻るのだ。
ただ露出度の高いドレスは避けたいな、と乙女心は考える。理由は傷が目立つから、ではない。
想夜はドレスの胸元を摘まんでは、乏しい胸に頭を悩ませる。
「こういう時って、やっぱり何か詰めるのかな? パット10枚とかバレーボールとか……入れるか。よし、いったろか」
「いったろか」じゃない。大きければいいってもんじゃないだろ。デカイのは武器とリボンと勘違いだけで充分だ。
ドレスは叶子が貸してくれたフリフリのフリル。ピンクと白の可愛いやつ。ティアラとかつけたらお姫様みたい、とか思っちゃうのは少女趣味の
「――ねえ叶ちゃん。胸、開きすぎじゃないかなあ?」
付き添いの叶子が隣から除き込んで想夜のドレスを整える。
「私と想夜じゃサイズが違うからね……あ、変な意味じゃなくて」
「意味的に胸のこと以外ないでしょ!」
想夜涙目。
「大丈夫よ想夜、Cでも充分魅力的よ」
ナマ暖かい眼差し。
「そ、そうだよね~。えへへ~」
Bですけどね~――と、さらに涙。
叶子のドレス。まことに残念なお知らせではございますが、想夜の貧しい貧しい、それは貧しい想夜のお胸では布が有り余ってしまうのでした。ションボリ。
「ちょっと待ってて。仕立てさんに直してもらうから――」
叶子がベルと鳴らすと、呼び出されたメイド軍団が現れ想夜を囲む。
「なななな、なんと? うわあああ!?」
とたんに想夜の体がメジャーでグルグル巻きになった。
ミイラ女と化した想夜のことを、腕組した叶子がニヤニヤしながら見物している。
「サイズは?」
「はい叶子様。えーと、バスト76センチ……ですね。アンダーは――」
「……Cじゃなかったのね」
叶子にバレた。
「ウエスト55センチ」
「折れそうね」
折れそうなほどに細くてしなやか、と脳内変換――ネガティブ思考はノンノン。何事も誉め言葉として受け取ろう!
「ヒップ80センチ」
「安産型……になれるといいわね」
「……あたし、叶ちゃんに何かした?」
想夜は笑顔でこめかみをピクリとさせる。
マウンティング? 女同士は笑顔で殴り合うというやつ? そうなの?
その場にいる全員にサイズが知られてしまった想夜。明日までに愛宮メイド全員の耳に届いているかもしれない。バカ発見器よろしく、女同士の井戸端会議は拡散レベルが尋常ではない。そうやって個人情報は漏洩されてゆくものなのです。
メイド達が忙しなく動き続けたおかげで、仕立て直しに時間はかからなかった。
作業を終えるとメイド達は部屋を出て行く。電光石火、迅速対応、24時間お電話お待ちしております。フリーダイヤル0120――それが愛宮メイドだ!!
ドレスに胸踊る想夜。スカートを摘まみ上げ、鏡の前でヒラリと回ってみる。
「うわぁ、可愛い~! こんなの着るの初めて♪」
「素敵よ想夜。妖精のようだわ……もともと妖精か」
「あはっ。叶ちゃんうまーい!」
キャッキャと笑う。
「ほら、はしゃぐと淑女が台無しよ」
叶子がポニーテールのリボンを直す。淑女たるものスカートの裾を翻させることなく歩くのがモットー。
「あ~ら叶ちゃん様、ごめんあそばせ。おほほほほっ」
即席でどこかの婦人みたく振舞う。
「そんな笑い方する人、実際にはいないけどね」
「え、そうなの?」
うん、アニメの見すぎですわよ。
想夜は不満気にドレスをつまんで引き上げ、足元に目をやる。
「叶ちゃん、つま先が痛い」
「ヒールに慣れてないのね、ちょっと待ってて」
ヒールだと歩きづらいのでパンプスに変えてもらう。てか、いつの間にか叶子がムチを握りしめていた。外国の教師が持っていそうな、悪い生徒の手や尻をビシッてやる痛そうなヤツ。
(はて、何に使うのだろう? まさか――)
想夜は少し青ざめた。
「叶ちゃん、その鞭ひょっとして……うう、うあああああああああ!?」
想夜は脳内に描いた予想が外れることを祈った、が無意味だった。
パーティーの嗜み 監修:愛宮叶子
歩き方の練習――女はみな乙女。女はみな淑女。乙女淑女たるもの優雅に、つつましく、それでいて華麗に歩きましょう。
叶子の指示のもと、部屋の中を行ったり来たりと往復する想夜。頭の上に分厚い百科事典をのせ、落ちないようにバランスを保ちつつ進んでゆく。が、10冊も乗せる必要あるの? 結構重い。1時間後には身長が5センチくらい縮んでいるかも。
叶子が手にしたムチをビシビシ振り回す。
(アレで殴られたら絶対痛いな。まさか本当に殴ってはこないだろうけど)
想夜は早くもチビリそう。
叶子が声を張り上げる。
「ほら背筋、ピンと伸ばす!」
「はいっ」
ピーン。
「ガニ股になっている!」
「はいっ」
キリッ。
「笑顔!」
「へいっ」
ニヤリ。片側の口角だけ吊り上げる。「ところで越前屋、例の黄金菓子は……」「ヘイお代官様、こちらにご用意してございます」「ほほう~、どれどれ」――笑顔というよりほくそ笑む感じ。当然、叶子がそれを見逃すはずもない。
「ワル者の笑みになってる!」
「はいっ」
にっこり。いつもの笑顔。
「ほらほら、頭の本ズレてる! 落としたらお仕置きよ~?」
叶子の手にしたムチがひしゃげる。
「ふえええええっ」
ビシ! ビシ!
「ふええええええんっ」
リボンの妖精、泣いても許されず。
叶子のスパルタは続く。
その後、本当に何発もケツを叩かれた……。
叶子と小さな番犬
17:30
「なあ叶子、本当に大丈夫なのか?」
「さっきから言っているでしょう。この通り、ピンピンしているわ」
病院から帰った叶子の安否を心配した狐姫は、昨日から同じ質問ばかりを繰り返していた。
ドレスに身を包んだ叶子は問題なさそうに振舞うが、病み上がりのためか、正直なところ狐姫の護衛は心強かった。
『あの人』に関する事だが、実のところ叶子もその正体を知らなかった。叶子とコンタクトを取る時は決まってメモを残し、「手遅れ」だと最後のメモを残した時でさえ、声すら聞けずじまいだった。
その事で力になれなくて残念だと、叶子が謝罪。
狐姫はそれを責めることなどしなかった。のんびりいこうぜ、と八重歯を見せて笑う。
狐姫の笑顔が叶子を次の行動へと駆り立てる原動力になった。
狐姫は叶子の部屋で見張り番。耳も尻尾も出しっぱなしだが、コスプレとしか見られない安心のケモノクオリティー。
メイドに囲まれる叶子がドレスアップされる度、狐姫の視線がチラ、チラ、とそちらを向く。
狐姫も女の子、オシャレに興味がないわけでもない。しかしながら、自分がドレスを着た姿を想像するたび、似合わない、と軽い吐き気すらもよおす。
時折、インカムから聞こえてくる御殿や小安の声に適当に返しては暇を持て余す。異常がなければいいんだろ、と。
叶子がドレスに着がえると、メイド達は会場の支度に向かう。やることは山ほどあるらしい。
先ほどまでうるさかった部屋に叶子と狐姫だけ残された。
ドレスアップした叶子。にじみ出る品格――名は体を表すように、衣服も身にまとう人間を表すもの。ドレスに身を包んだ叶子は、本物のお姫様みたいだった。
狐姫が見とれていると、叶子が笑みを送ってきた。
「狐姫さん。退屈でしょうけれど、護衛のほう、頼りにしているわ」
「おう、任せとけ」
隣の部屋には想夜がいる。先ほどまで叶子と一緒にいたようだが、「やーん!」とか「痛~い!」とか悲鳴が何度も聞こえたので気にはなっていた。が、想夜なので心配することもないだろう。どうせゴキブリでも発見して騒いでいたに違いない。それをビシビシと棒状のようなもので殴っていたのだろう。んでもって勢い余ってタンスに腕をぶつけたのだ。きっとそうだ、そうに決まっている。腕をぶつけて可哀想だな、プププッ――狐姫ちゃんサマ、思わず吹き出しそうだぜ♪
他者を笑うものは他者に笑われる。狐姫に試練の時が迫っていることに誰が気づいているのだろうか?
叶子が狐姫の前に立つ。それも裏のある笑顔で。
「それじゃあ狐姫さん、袴のポケットから手を出して」
「は? なんで?」
「そんな格好で歩いてたらチンピラみたいでしょ? これからパーティーなんだから。はい、まずは歩き方の練習から――」
狐姫の体が硬直した。
パーティーの嗜み その2 監修:愛宮叶子
レッスンスタート!
「――な、なんで俺がそんなことを……」
ズドン!
「ぐえ!?」
問答無用。抵抗むなしく金髪の上に百科辞典20冊くらい乗せられた。その重みで狐姫の目ん玉が飛び出しそうになった。
「フザケンナよな! なんだよコレ? ルイージに踏まれたマリオみてーになってるじゃん俺……って、何それ? なんでムチ持ってんの? ……ねえ?」
鞭を手にした叶子が赤い目を光らせながら、狐姫に近づいてきた。
迫る影。
狐姫の泣き叫ぶ声――
「ちょ、ちょっと待て叶子、話し合おう! やっぱ暴力ってサイテーだよな? ね? そうでしょ? 話し合…………ぉぅぎゃああああああああああ!?」
淑女に一歩近く狐姫だった。
10分経過――。
「くっそー、人の尻バンバン叩きやがって! こんなに背筋が伸びちまったじゃねーかっ」
背筋がピンと伸び、普段はポケットに入っている手も手前で合わせでお淑やか。少しは淑女らしくなったようだ。
狐姫よ、やればできるじゃないか。
痛てててて、狐姫が頭と腰をさすっている。
「身長、まさか縮んでないだろうな」
もう百科事典は乗ってない。
頭スリスリ。身長は問題なさそう。口を尖らせながらドレッサーに戻り椅子に座る――もちろん足など組まない。お人形さんのように大人しく、お淑やかに膝を閉じる。また叶子に何されるかわからないのでヒヤヒヤしている。
鏡の前にたくさんのメイク道具や基礎化粧品が並んでいるのが目に付くと、狐姫はその中のひとつを手にした。
「なあ叶子、コレなんだ?」
狐姫が手にしたのは基礎化粧品の容器。見たことも無いビンに入った液体。化粧水というやつだ。それをジュースか何かのようにシャカシャカと振って遊ぶ。
「化粧水よ。狐姫さんは使わないの?」
「んなもん使うかよ、メンドクセー」
「御殿さんは使ってないの?」
「う~ん、使っていたような使っていなかったような……」
興味がないことは全てスルー。思い出せませーん。
叶子が狐姫のホッペの状態を手でさぐる。
「どれどれ……」
「うわっ、なに?」
ぷにぷに……。
狐姫のホッペはキメが細かくて赤ちゃん肌。くすみは無く、透明感があり、化粧水など必要ない。
想夜と華生も同じような肌の持ち主なので、妖精や妖獣は人間離れした肌を持っているのだと叶子は実感する。
「狐姫さん、ちょっとこっちへいらっしゃい」
狐姫を洗面台に立たせて洗顔させると、手に取った化粧水をホッペにあてる。やはり若干弾くようで化粧水などいらない。肌が水分を保っているのが分かる。
それでも叶子は両手に化粧水を広げ、狐姫のほっぺに優しくすり込む。てのひらでフタをするように、ジワ~ッと肌に吸収させる。このほうがパッティングするよりも効果的である。
狐姫は気持ちよさそうに目を閉じている。
「なんか……冷たくって気持ちいい。それに、ほんのりいい香りがする」
淡い花の香り。
初めての化粧水。初めてのスキンケア。自分の顔がどうなってゆくのか興味がわく。
いつもは洗顔料でワシャワシャと顔を洗って、それでおしまい。けれど今回は化粧水でおめかし。ちょっと背伸びしたキブン。それが終わる頃には狐姫のホッペは普段にも増して輝きを増していた。
鏡に映る自分の顔がいつもと違う。なんつーの? ほっぺが光を放っているってゆーか……なんかスター取ったみたいに光ってる?
狐姫はうまく表現できないでいる。手の甲で頬を触ってみるが、やはりいつもの質感とは違ってプルンとした感触、その行為にやみつきを覚える。
「うお、何コレ!? ほっぺたツルッツルじゃん! 魔法のアイテムじゃね?」
狐姫ちゃんビックリ。
「お気に召したかしら? 乳液もつけたいけれど、狐姫さんの肌、油のってるからつける必要ないのよね。ベトベトするのはイヤでしょ?」
「イヤ」
狐姫は顔に納豆を塗られる想像をしてゾッとする。
「化粧水だけでこの輝きを出せるなんて、世の女性を敵に回しているようなものよね」
「そうなのか?」
キュッキュと肌をさすっている。自分の肌の価値を全然わかっていないらしい。
「狐姫さんがドレス姿ならメイクもしてあげたのだけれど、今はこれでガマンしてちょうだい」
叶子はリップを取り出すと前かがみになり、狐姫の唇に塗ってゆく。右から左へ、左から右へ。唇が透明な輝きを増していった。
「ん~」
叶子が唇を閉じて見せる――同じようにしなさい、と狐姫にうながすと、
「ん~」
狐姫も叶子に習い、唇を閉じてリップを広げた。
「――はい完成」
つややかな唇。けど、なんだかベトベトするので違和感がわく。
「なんか、ベトベトするな」
「御殿さんも喜ぶわよ」
狐姫が眉をハの字にする。
「なんで御殿が喜ぶの?」
「御殿さんのこと、好きなんでしょ?」
「ははっ。好きも嫌いもあるかよ、嫌いだったらコンビなんか組まねーよ」
「そういう意味じゃなくて……」
叶子は少し考えると言い方を変え、狐姫の耳元でそっとささやく。
「御殿さんとキス……したくない?」
狐姫が驚いて飛び上がる。変な悲鳴をあげて椅子からずり落ちた。
「ババババ、バカなこと言ってんじゃねーよ! なんで俺がアイツと、アイツと……」
キス、しなきゃなんねーんだよ――と言いかけて、口を閉ざした。顔が紅潮してロレツが回らない。叶子の言葉は、そのくらい狐姫の心を揺さぶりをかける言葉だった。
「だだだ、大体、御殿は女だぜ? 女同士でキスとかないわー」
ははは、と目が泳ぐ狐姫に叶子の顔がズイっと迫った。
「愛宮の力を舐めないで頂戴。御殿さんの性別くらい、とっくにお見通しよ」
ギクリ! 狐姫の体が硬直する。
「マ、マジで?」
「マジマジ、大マジ」
「御殿が男だってこと……知ってたの?」
それを聞いた途端、叶子は安堵のため息、というべきか、呆れた感じのため息というべきか――まあ、そんな感じのため息をつくわけ。でもって苦笑しながら肩をすくめる。「まさか本当に男だったとはね……」、と言いながら。
それを見て狐姫がキョトンとする。
「は?」
そうしてやっと気づくのだ、叶子に一本取られた、と。
「カマをかけた……のか?」
「ええ。簡単に引っかかってくれて何よりだわ」
叶子、ドヤ顔。
狐姫がイスに座りなおす。
「なんで男だと思ったの? いつから感づいたの?」
「女の感、って言いたいところだけれど……今は秘密」
「なんだよソレ、気になるだろ、教えろよ!」
叶子は狐姫をからかって遊んでいるかのよう。
狐姫はそういう叶子の悪戯好きなところも好きなのだ。ドレッサーの前で拳を振り上げるマネをする狐姫、それを手で庇う素振りを見せる叶子。
笑顔でふざけ合う2人は、だだの女の子に戻っていた。
無数の擦り傷
18:29
ドレスアップした叶子に護衛として狐姫が同行する。2人して会話を続けながらパーティー会場へ向かっていた。
「なあ、本当に御殿を任務からはずさない?」
自分の失態に責任を感じてか、狐姫は叶子に問う。男だから学園の任務から外す、という答えが恐ろしいのだ。それでも叶子は平然としていた。
「心配御無用。今のまま護衛を続けてちょうだい。約束どおり、御殿さんのことも黙っておいてあげる」
「さっすが叶子、話がわかるぜ~」
狐姫の顔がぱあっと明るさを取り戻す。
「ハイヤースペックを発動すれば、スペクターの私も完全な女じゃなくなるし」
ボソリ……叶子がつぶやく。お嬢様は悩みが多い。
狐姫がインカムで連絡をとっている。相手は御殿だ。
「もしもし、こちら狐姫ちゃん。どうぞ――」
ぶっきらぼうに応答すると、インカムから御殿の声が聞こえてきた。
『狐姫、そちらの状況を教えて――』
「異常なし。叶子の着替えも済んだ。今から会場に向かう。叶子のパンツの色教えようか?」
「是非ともやめてね」
叶子、軽蔑の眼差し。狐姫が苦笑してたじろぐ。
『了解、そのまま護衛を続けて。 プツ……』
インカムを切られたようだ。見事に無視された模様。
「おい御殿、無視すんなコラ! ……あーもう、叶子の顔が怖えーんだよっ」
ひとりインカムに叫ぶ狐姫。天真爛漫な姿は、想夜とは一味違って面白い。
「くっそ。御殿のヤツ、スイッチ切りやがった」
「好きな人の前で他の女の話をしたらマズイでしょ、さすがに」
ポツリ。叶子は額に手を置いてつぶやいた。
「え? なんか言ったか?」
「何も言ってませーん。会場までの護衛、よろしくー」
叶子は笑顔を狐姫に向けた瞬間、目の前の光景に目を丸くした。
ブシャアアアアアア!!
突然、狐姫が背中から鮮血を撒き散らしたのだ。
窓ガラスについた狐姫の血が滴り落ちる。
「なん、で……俺――」
なにが起ったのか理解できないといったリアクション。狐姫は固まる表情のまま、叶子を見つめ、ゆっくりと前のめりに倒れこんだ。
「ウソ、だろ? ……誰も、いなかった……ハズ、だ」
「狐姫さん!」
スローモーション再生を見せられているように崩れてゆく狐姫の体。それを叶子は見届けていた。
廊下に人の気配はなかった。
確かになかった。絶対なかったと言っていい。それくらいに確信が持てた――誰の気配も、なかった、と。
叶子は狐姫のインカムを奪うとスイッチを入れて叫んだ。
「御殿さん聞こえる? こちら愛宮叶子! 聞こえる? 返事をして御殿さん!」
ザッ――しばらくノイズがはしり、御殿の声がクリアになった。
『こちら咲羅真。叶子さん? どうしました?』
「狐姫さんがやられたわ!」
『……』
返答なし。耳に届いた内容を疑っているのだろう。無理も無い、無敵の相方が後ろから、それもたった一撃で仕留められてしまったのだから。
どうこうしている余裕はない。叶子は狐姫の治療を優先したかった。
『もう一度、お願いします』
御殿のゆっくりとした口調がインカムから響いてきた。深呼吸でもしているのだろう、少し冷静になって次の手を考えているようだ。
叶子はもう一度、起った惨事を叫んだ。
「御殿さん、いい? よく聞いて。狐姫さんがやられたわ!」
インカムに叫ぶのと同時に狐姫が起き上がってきた。
その体を叶子が慌てて制止する。
「狐姫さん、傷口が開いてしまうわ。まだ動かないで!」
「叶子、俺の傷口……どうなってる?」
この血の量だ。傷は深いに決まっている。けれども狐姫を焦らせてしまわないよう、叶子は気づかった。
「大丈夫よ、すぐに治療すればね。肩を貸すから私の部屋に行きましょう。歩ける?」
狐姫は叶子の親切心を嫌がった。
「いいよ、血で……ドレスが汚れるから。せっかく、綺麗……なのに――」
「バカね。あと1000着残ってるわ」
かまうものですか、と叶子は狐姫に肩を貸した。
「格差社会に……異議をとなえたいぜ……」
叶子は狐姫を自室まで連れて行くと通路に首だけ出して安全を確認。扉を閉め、そのまま床にうつ伏せに寝かせた。
上着を見ると背中に一撃、日本刀でバッサリと切られたような一閃が服に残っている。服を脱がせて傷口を見ると、やはり斜めに一本、鋭利な刃物で斬られたであろう傷痕が残っていた。
叶子は手元のベルと鳴らす。ちょっと不思議な鳴らし方――独特のリズムを刻むことで駆けつける使用人を決めてある。
――やがて誰かが扉をノックする音。
「お呼びでございましょうか、お嬢様」
部屋に入ってきたのは華生だった。
目に飛び込んできた光景に、おしとやかな声の華生がハッと息を呑んだ。
「狐姫さま!」
「華生、すぐに狐姫さんの応急処置を」
華生は大きくうなずく。
「かしこまりました、お嬢様」
華生は血まみれになった狐姫の衣服を剥ぎ取ると、背中の血を拭きとってガーゼを当てた。その後、慌てて部屋を出てゆき、手ごろなビンを大事そうに抱えて戻ってきた。
「妖精界に伝わるお薬です。痛み止めの効果もありますし、治りも早いでしょう」
華生は透明な液体を狐姫の傷口に、丁寧に、丁寧にすり込んでゆく。
「……ん? これは――」
途中、異変に気づいた華生はピンセットを手にした。
傷口に触れると痛むのか、薬がしみるのか、はじめのうちは小さなうめき声を上げていた狐姫だったが、やがてその声もしなくなった。
傷口を見た華生は目を細めた。なにかに気づいたようだ。狐姫の止血を済ませると、背中をガーゼで覆った。
「華生、どうかして?」
叶子が問うと、華生がとつぜん服を脱ぎ始めた。体中につけられた傷を見せたかったのだ。それが何よりの証明になるのだから。
「華生、その傷は――?」
叶子は目を見開いた。華生の体には無数の引っかき傷が残っていることに驚きを隠せなかった。工場跡で一悶着あったとは聞いていたが、これほどのダメージを受けているとは思わなかった。しかも深さは違えど、狐姫の背中にも華生の傷と全く同じものがついている。
「この傷は赤帽子に受けた傷です。深い傷ではありませんが、直撃を受けると相当のダメージになるでしょう」
そう言って狐姫を見る。目の前に直撃を受けた体がある、と訴えてくる。
「でも廊下には私と狐姫さんしかいなかったはず。どうやって斬ったの?」
叶子の言葉の途中、華生は何かの破片を差し出した。
小型の1センチ四方ほどのピンクの破片。先ほど、ピンセットでつまみ出したものだ。
「それは?」
「狐姫さまの背中に入っていたものです。先ほど摘出しました。気をつけてください」
華生は破片を叶子に手渡す。
硬くて、ガラスの破片のように尖っているけれど、そうじゃない。プラスチックの破片のようだけど、そうじゃない。
「これは……動物の爪!?」
「はい、赤帽子の爪です。どこかで狐姫さまの背中に仕込んだのだと思います」
「どこかって……まさか!?」
叶子は思いを巡らせる――そう、あの時。学園の屋上で、狐姫が自分のことを庇ってくれた時のことを。衝撃波を喰らった狐姫が「背中がチクチクする」と言っていた時のことを思い出したのだ。
「あの時から狐姫さんの背中に爪が仕込まれていたというの!?」
事情を聞いた華生が大きくうなずいた。
「はい、爪自体が衝撃波だったのです。後から奇襲をかけるための攻撃であったことには違いありません。現にこうして、敵の作った青写真の中にわたくし達は入っているのですから」
敵の手中に入っている。それを聞かされた叶子は目を吊り上げ、歯をギリリと噛み締めて拳を作る。
「ぬかったわね」
今にもハイヤースペックを発動させそうな勢いだ。
叶子の怒りを華生がなだめている。
そうこうしているうちにノックの音――御殿が駆けつけてきたのだ。
「狐姫!」
御殿は視界に飛び込んできた光景を前に、血の気がひいた。なんと狐姫が血まみれで横たわっているではないか。
「狐姫! 狐姫、大丈夫!?」
狐姫の手前、傷ついた体に触ってよいものか、動かしてよいものか。
「狐姫さんなら大丈夫よ。華生が治療をしたわ。しばらく安静にさせてあげて」
御殿を狐姫から遠ざける叶子。
御殿はただ叶子の言葉に従うしかなかった。
「――すみません、守るべき者が守られるという醜態をさらしてしまって……」
落ち込む御殿を見かねた叶子が肩をすくめた。
「そういう時は『治療してくれてありがとう』でしょ? 友達なんだから。華生もそう思うでしょ?」
「もちろんでございますよ、お嬢様」
ニコリと微笑む。華生はいつも叶子を見守るようにそばに立っている。
それを見て御殿は思うのだ――華生のように狐姫のそばにいれば相方を救えたのだろうか、と。自分はまるで牙を抜かれた狼のようだ。最近、失態を繰り返してばかりのようにも思える。御殿は自分を責め立てた。
ちょうどその時だ。
『……!』
『……!!』
隣の部屋から物音が聞こえてくるではないか。
何事かと皆が耳を澄ませた。
「騒々しいわね、何かしら?」
叶子と御殿の目が合う。
隣には想夜がいるはずだ。今、何かが起きているらしい――。
「隣の様子を見てきます」
「お願いするわ御殿。狐姫さんの事は任せて」
「すみません」
「ありがとう、でしょ?」
「あ、ありがとう……」
出てゆく御殿が少し照れ気味に目をそらす。そういうところがイジられやすい。
ピンクのマニキュア
18:20
レッスン終了後、想夜はひとりドレッサーの前にヘタレこんでいた。
叶子はドレスアップのために自室に戻った。今頃は狐姫と一緒に会場に向かっているはずだ。
「あ痛たたた……もう! 叶ちゃん、本当に叩くんだもんっ。スパルタ指導に異議あり!」
プンスカピー! 想夜がブーたれている。
力加減にせよ鞭は鞭、想夜をビビらせるには最高のアイテムだった。
幾度となく繰り返されるスパンキングだったが、ミミズ腫れにならなくてよかったと思う。想夜は頭の上の百科事典を下ろし、フンヌー! と仰け反って腰を伸ばす。身長が縮んでなくて何より。
と、そこへ――
コンコン。
誰かが扉をノックする音――叶子だろうか?
「はーい、どうぞー」
想夜が扉を開けた瞬間、その顔がこわばった。
「あ、あなたは――」
「お邪魔させてもらうわね」
部屋に入ってきたのは鹿山だった。
「詩織、さん」
後ろでに扉を閉める鹿山。
密閉空間が想夜の不安を増幅させていった。
想夜は身構え、些細だけれど軽蔑の眼差しを送る。また何かされるのではないかと勘繰る。
それを見た鹿山が肩をすくめて申し訳なさそうに眉尻を落とした。
「想夜さん、この間はごめんなさいね」
「……いえ」
視線を逸らし、言葉とは裏腹に想夜が後ずさる。詩織には良い感情を持っていない。
「想夜さん可愛いから、ちょっとからかってみたくなっちゃって」
女子トイレでの出来事――初対面の冗談としてはキツすぎる。人の太股に足を刷り込ませたり、耳に吐息を吹きかけたり。想夜が嫌悪感を持つのも無理は無い。
「あたし、可愛くなんて……ないです」
少しふて腐れた対応をしてみる。そういう素直なところがサディスト心をくすぐるのかもしれない。ある意味、自業自得。
怯える想夜の手を取ってマジマジと見つめてくる。
「綺麗な手をしているのね。透き通るような肌の色……爪はお手入れしているの?」
「ハ、ハンドクリーム……くらいなら。あと、ボディクリームとかもいい香りがして……好きっていうか、興味あるっていうか――」
恐る恐る、上目使いで答える想夜。
「香水は?」
「香水は匂いが強いっていうか……使わない、です」
「ボディクリームはいい香りのが揃ってるわよね。駅前のお店はテスターも揃っていてオススメよ」
「そんなお店があるんですか……今度行ってみようかな」
うわー、何この人ー。女子力たかーい。沙々良さんも酒ばっか飲んでないで見習って欲しいものだ。
日本では町娘や芸者などが匂い袋を懐に忍ばせていた。香りとは魔よけとしても有名だ。
世の女性たちは旨い肉を身につけている。皆、魔物に食われぬよう気をつけなければならない。
魔物はいい香りが嫌い。悪臭を好む存在である。
想夜は思うのだ。願わくば、香りが詩織の魔よけになるように、と。
「……爪は伸ばさないの?」
「料理の時に邪魔になるから、切ってます……御殿センパイも伸ばしてないですし」
「御殿センパイ? 咲羅真さんのことね」
詩織はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「好きなの?」
そう言われ、とたんに耳まで真っ赤になる想夜。
「お、女の子同士ですよ! 好きとか、じゃないです……」
「料理のことを聞いたんだけれど……」
「は!」
完全に墓穴を掘った。御殿の性別をごまかすため、己の感情をごまかすために頭がいっぱいだったから仕方の無いこと。けれど、からかわれた感が匂ってくるのは気のせいだろうか?
(――この人、やっぱりイジワルだ)
想夜の頬がブゥ~と膨らんだ。ちょっと怒ってるんだゾ、的な顔。
詩織は構わずに懐から小瓶を取り出した。中の液体、キラキラ光るラメが可愛い。
「マニキュア、塗ってみる?」
屈託のない笑顔で想夜に見せた。
「……い、いいですよ、別に」
興味はあるけど断った。が、やや後ろ髪を引かれる思い。可愛いものやオシャレに惹かれるお年頃。
「せっかくドレスアップしてるんだし、きっと似合うわよ」
「で、でも……」
「大丈夫、透明な光沢をつけるだけだから」
想夜は手をとられ椅子へ導かれた。まんざらでもなさそう。
「それじゃ、じっとしててね」
ぴくんっ。
指先が敏感に反応し、頬が火照る。
体をななめに傾け、逃げるような素振りをとって顔を背けるも、横目でチラッチラッとマニキュアの筆の行方を追ってゆく。
爪に塗料が塗られてゆくたび、想夜の子供じみた爪が光沢さを増し、甘い蜜を塗ったようにキラキラ光り始めた。きっと森のクマさんも甘そうな蜜に誘われてくるだろう。
想夜だって普通の女の子。輝きはじめた自分の爪を見て、「あ、なんかキレイ」――とか目を輝かせたりなんかして。
次第に慣れてきたのか緊張がほぐれ、強張った体から力が抜け、少し楽になった気がした。
続いて詩織がピンクのマニキュアを取り出した。
「これはおまじない。好きな人と結ばれるように、ね――」
左手小指の爪を淡いピンク色のマニキュアで彩った。
「好きな人……」
ポツリ。想夜は口にした。
たぶんその人、今は仕事中だ。働き者、けれど、あの人はドレスを着られない。オシャレする時間も許されない。それが気の毒に思えた。
光沢を得た想夜の爪は、自分の手じゃないみたい。ほんのりと色づくその輝きは、想夜の恋の行方を応援してくれるようだった。恋の迷路で迷わぬように。引き裂かれようとも、想い、揺らがぬように――と。
「――がんばってね、想夜さん」
ほんのり香水のいい匂い。
立ち去る横顔に寂しさを感じた。研究所の女子トイレで、彼女はなぜあんな行為に及んだのだろう?
嫌悪感で満たされていた詩織への感情はどこへいったのか、想夜は消え行く背中に愛着さえ湧いていた。
詩織が退室してすぐのこと。
コン、コン……
ふたたびノックの音。今日はやけに慌ただしい。
「はいはーい♪」
もうすぐパーティーがはじるというのに。
「パーティーだから忙しいのは当たり前、なのかな?」
爪を眺めていた想夜がドレスの裾を直しつつ立ち上がる。こういう賑やかな体験は初めてなもんだから不慣れである。
いそいそとドアに駆け寄る。
コン……コン……コン……コ、コン――。
ふたたびノック。おかしなリズムでやけに急かしてくる。いったい誰だろう?
「はーい、いま開けまーす」
想夜がノブに手をかけた。その時だ。
コン……コ……カリッ、ガリリリリリリリリリリリリリリリリ……!
ただならぬ音と気配にゾッとして後ろに飛んで扉から離れようとした――理由は明白、血の匂いがしたからだ。
血の臭い。鉄臭い――。
扉の向こうを睨みつけながら後退しようとした瞬間、ドンッと音を立てて想夜の体がくの字にひしゃげ、真横に吹き飛んだ!
「ぐえっ!?」
扉とは全く別の方角からの攻撃。想夜が扉の向こうに警戒した隙をつき、べつの誰かが窓から侵入していたのだ。
想夜の視線が敵を捉えた。
「赤帽子!? やっぱり来たか!」
カーペットに横たわる想夜の顔が強張る。先日、廃墟で逃がした赤帽子が奇襲をかけてきたのだ!
立て続けに扉からもう一匹の赤帽子が乱入。扉の向こうからの異質な音は鉤爪で引っかく音だった。長い爪を使って後ろ手に鍵を閉め、ニヤリと口元を吊り上げる。騒ぎが大きくなる前に想夜を始末するつもりだ。
「2匹、か」
赤帽子が会場に入り込めば大騒ぎになり、折角のパーティーが台無し。そうならないためにも、想夜がここで食い止めなければならない。
パーティー中止だけならまだマシなほう。犠牲者を出そうもんならMAMIYAも後々厄介なことになる。それ即ち、叶子を追い込むことにもなるのだ。友達として、それだけは避けたい。
想夜が天高く片手を突き出す。
「ここで……喰い止める!」
エーテルバランサー想夜よ、犠牲者を1人として出すな!
背中の羽を広げ、胸のベルトがπスラッシュを作った。
ズシリと背中にひびくワイズナーに手をかけつつ、想夜は敵との距離を一定に保つ。
背中のワイズナーを抜くか抜かぬか――
にらみ合いが続く――。
1対2。秒針が時を刻んだ瞬間、赤帽子との対決が始まった。
「来い!」
想夜はワイズナーを引き抜き、矛先を赤帽子に向けて挑発をする。
一匹ずつでも同時攻撃でも何でもいい、かかって来い! ここで蹴散らしてやる!
2匹の赤帽子は想夜の目の前から姿を消した瞬間、左右から同時に斬りかかって来た。
「はっ!」
想夜は大きく後ろに仰け反り、床に片手をついてバク転、着地。うまく避けることができた。その後、テーブルを蹴り上げて敵の視界を殺し、ひるんだところへ足払いをかます。ドレスだと少し動きにくい。やっぱミニのほうが動きやすいと実感する。
足払いを喰らった赤帽子が床に横たわる!
そこへ想夜がワイズナーを振り下ろす!
が、赤帽子は横になった体をゴロンと回転させてこれを回避!
「くっ、やっぱ速い!」
敵が回避した場所へすかさず想夜がワイズナーを振り下ろす! が、またもやゴロゴロと転げまわり、回避しては致命傷を避ける。
そんなことを5回6回と繰り返しているうちに、もう一匹の赤帽子に背中をとられてしまい、想夜の体が一撃で弾き飛ばされた。
ボフッ!
「うぐっ!?」
斬りつけられた想夜は背中からベッドに突っ込んだ。
そこへ赤帽子の一匹が飛び込んでくる。
相手との距離を計った想夜は、つかんだ枕を赤帽子に投げつけた!
「これでも食らいなさい!」
赤帽子が飛んできた枕を一瞬で切り刻むと、中身の羽毛があたり一面に飛び散る!
羽毛が舞って視界が悪い。ベットの
想夜は目を凝らして敵の出方を見るが、赤い爪は目がくらんだ想夜を容赦なく斬り付けてくる。
ザシュ、ザシュ!
ベッドに爪がめり込む音。
突き刺してくる赤い爪を、想夜は頭を左右に振って回避。
隙を突いた想夜、ベッドに食い込んだ爪で動きが鈍る赤帽子の手首をつかんで動きを封じると、相手の腹にケリを入れて天蓋近くまで吹っ飛ばし、落下してきたところへ再び蹴りを入れてベッドの外へ飛ばした。
息つく間もなく、今度はベッドの下から物音がする。
(下にもいる!?)
想夜がベッドの下に注意を向けると、シーツの向こうから爪が飛び出してきた!
想夜の顔のすぐ横、顔面スレスレを爪がかすめる!
ツゥ……、薄っすらと頬に一本の赤い線が浮かんでは涙のように垂れる。あと数ミリずれていたら頭を串刺しにされていたところだ。
想夜が避けた場所へ、さらに爪が突き上げてくる。それを器用に首を捻ってはかわすリボンの戦士。
「そこ!」
ドス!
ベッドの下から飛び出してきた爪が引っ込むと同時に、その場所へすぐさまワイズナーの矛先をブッ刺す!
ベッドの下でゴロリと体を捻って回避する音が聞こえた後、その隙間から赤帽子が転がって出てきた。冷蔵庫の裏に殺虫剤を散布したらデカいゴキブリが出てきたみたいに。どうやら攻撃は当たらなかったらしい。
ベッドの上は危険だ――想夜はベッドからワイズナーを引き抜き、仰向けの姿勢のまま両足を天井にあげ、あげた足を振り下ろす。その反動で起き上がると、羽を使って少し離れた床の上に着地する。
部屋の中、想夜と赤帽子がにらみ合い、平行を保ったまま走る!
ドレッサーの前を通過する瞬間、後ろから赤帽子が襲ってくるのが鏡に映った。
想夜は化粧水のビンを手に取ると、赤帽子に投げつける!
敵が避けるのは想定内、真横へ避けつつ突進してきた赤帽子の顔面目がけ、今度はチューブの容器につまったボディークリームを搾り出して目くらましを見舞った。
「お願い……出て!」
ぶちゅうううう。
イキのいい立ちションのように構えた想夜の両手の隙間から、ピューピューと白い液体がほとばしる!
「ギャ!?」
赤帽子のおかしな悲鳴が上がる。どうやら目にクリームが入ったようだ。
想夜のみごとな顔面シャワー。あまりの勢いのよさに自分の顔面にもかかってしまう。
視界を殺された一匹の動きが鈍ったのをこれ見よがしに、想夜は足元に転がっていたゴミ箱を蹴飛ばして2匹目の足元を狙う。
転がってきたゴミ箱を飛び越えてきた赤帽子。そこに直線を描いたワイズナーを叩き込んだ。
ザシュ!
一閃。真正面からの一撃は致命傷だった。肩を突かれた赤帽子は後ろに吹っ飛んで崩れ落ち、ビクンビクンと痙攣している。
続いてクリームまみれの一匹にもトドメを刺そうと敵に近づく想夜だったが、思わぬ事態が起った。なんと赤帽子は自分の爪をはがし、クナイのようにサイドスローで投げつけてきたのだ。
「飛び道具!?」
体を張った飛び道具。想夜は顔面めがけて飛んできた爪をギリギリのラインで避けた。が、鋭い爪が一本、二の腕に突き刺さる。
「痛っ!」
二の腕でよかった。目に直撃を食らっていたら失明していたところだ。
「ううっ、けっこう深く刺さったなあ」
想夜は腕に刺さった爪を、なるべく神経に触れないようゆっくり引き抜いた。そのまま体勢をくずし、タンスの脇に寄りかかる。
そこへ赤帽子がすごいスピードで突っ込んできた。想夜の首をかき斬るつもりだ。まさに捨て身の攻撃だった。
「殺られる!」
恐怖した想夜は目を閉じ、両腕で顔を庇った。
「…………………………」
異変に気づいたのはその後のこと。想夜は恐る恐る片方の瞼を開けて様子を伺う。
どうしたことだろう、赤帽子の体がグルンと空中で一回転して床に叩きつけられていた。
その後、倒れる赤帽子の腹に一発、黒い影は長い足を使って空き缶をふみ潰すようなヘコマシを入れて気絶させた。
はじめは想夜自身が引っくり返ったような錯覚に陥ったが、決してそうではない。そうして想夜は気づくのだ――目の前にいる黒い影に命を救われたという事に。
「想夜、大丈夫?」
視界がぼやける。黒い影がこちらを見ている。想夜のことを見ている。
手を差し出してきて、起きるのを手伝ってくれる。そうやって、いつも優しい眼差しをくれる人――。
「御殿、センパイ……」
目の前に飛び込んできた黒い影は御殿だった。赤帽子が想夜に切りかかる瞬間、敵の手首を取って捻り、投げ飛ばしたのだ。赤帽子は弧を描いて宙返り、床に背中を叩きつけては大げさな音を立て、追加でケリを食らってダウン。
本当に一瞬の出来事だった。
――戦闘終了。
けれどいい話ばかりではない。
「想夜、狐姫が何者かにやられたわ」
「狐姫ちゃんが!?」
「背中を斬られた。おそらく赤帽子ね」
どういうこと? 赤帽子ならたった今、倒したばかりだ。
狐姫を襲ったのはコイツらなのか? それとも別の赤帽子? ――横たわる赤帽子2匹を見ながら、想夜と御殿はそう考えていた。
部屋を見渡した御殿はため息をつく。ド派手にやったのが良く分かる。いろんなものが散乱し、ベッドも床も切り刻まれていた。凶暴な妖精というものを初めて見たが、どうやら尋常ではない戦闘力をお持ちのようだ。あんな奴らを50匹近く片付けた想夜と華生に敬意を表したい。
2匹の赤帽子を早急に帰界させた想夜は、御殿とともに部屋を飛び出した。
廊下を走りながら想夜が御殿に話しかけた。
「ドレス、汚れちゃった。叶ちゃん怒るかな」
「あと10000着くらい残っているらしいわよ。一着くらい破れても問題ないでしょ」
「格差社会に異議アリ! 異議アリ! 異議アリ!」
涙目想夜が叫ぶ叫ぶ。
御殿は廊下を走りながら、しょんぼりと肩を落として着いて来る想夜を励ました。ドレスの桁が少し違った気もするが、まあいい。想夜が無事で何よりだ。それより、折角のドレスアップが台無しになってしまったのが可哀想に思えた。ドレスを着てパーティーに出席――どれほど楽しみにしていたことか。女の子として、さぞかし残念なことだろう。
けれども悠長にはしれいられない。すでにここは戦場と化している。そのことを胆に銘じていくべきた。
想夜と御殿が叶子の部屋の扉を開けるとそこには叶子、華生、それにダウン中の狐姫がそろっていた。
叶子から事情を聞かされた想夜は、狐姫の背中から摘出された爪を華生から受け取る。
「想夜さま。この攻撃はやはり――」
想夜はそれを指で摘まんでマジマジと見つめ、こんなことを言った。
「――うん、『ザッパー』ですよ、これ」
「ザッパー? なんなの、それ?」
叶子が眉をよせた。
ザッパー――風の妖精シルフィードの力を借りて放つ攻撃。かまいたちのように鋭く、真空波や衝撃波に良く似ている。以前、叶子や華生と戦った時、振りかぶったネイキッドブレイドの風圧が触れただけで想夜の頬が切れたことがあった。エーテルと風圧を用いた飛び道具の一種であり、攻撃属性を持つ妖精ならば皆、威力は違えど使用可能だ。
想夜も攻撃属性の持ち主なのでザッパーを打つことが可能であるが、大量のエーテルを消費するし隙もデカい。撃った後に反撃を食らう可能性が大きいので極力使わないようにしている。
加減を誤ると危険な事態を招く。最大出力で無事だった妖精はいない。ザッパーは曲者芸だ。
「屋上での衝撃波の正体は爪。それ自体がザッパーになって飛んできたのね」
「それが狐姫の背中に残っていた――」
「はい。しかもスイッチを入れるように、好きな時に狐姫ちゃんの体内で再びザッパーを発動させることが出来たようです」
「ザッパーの遠隔操作? 誰もいないのに狐姫さんがやられたのはそういう理由だったのね」
敵は好きなタイミングで狐姫にダメージを与えることが出来たわけだ。
狐姫が身代わりにならなければ、犠牲者は叶子だったかもしれない。
つくづく相方に苦労をかけさせている、と御殿は責任を感じた。せめて自分が身代わりになればよかったのに、と悔やんだ。
「幸い、爪の食い込み方が甘かったのでダメージが軽かったみたい。ザッパーの発動方向も外へ向かってるから内蔵は無傷です」
想夜は狐姫の背中の傷を見ながら少し疑問を感じていた。
皆、胸を撫で下ろした。攻撃が内臓に向かわなかったのは不幸中の幸いだ。今回の出来事はラッキーだったと前向きに考えたほうがいい。次は無事じゃ済まされないかもしれないのだから。
「ザッパーか、いいこと聞いたわ。今度試してみるわね」
う~ん、と叶子が伸びをする。その背中に想夜が忠告しておく。
「えー、隙が大きいよ? それに疲れるし」
「一発で仕留めれば反撃も来ないでしょう?」
「まあ、そうなんだけど」
無理しないでね。想夜の心配は叶子に届いているのやら、いないのやら。
「それよりも想夜……どうしたの、その格好?」
ジト目の叶子が想夜に向かってズズイッ! と迫ってくる。なんか目が据わってて怖い。
「じ、実は――」
想夜は先ほど起った戦闘を皆に説明した。
「ごめんなさい、ごめんさい!」
グチャグチャになったドレス。所々に赤帽子に切られ、いい塩梅でスリットが入っている。でもってひたすら平謝り。
「まあ、無事ならそれでいいんだけど」
叶子はクローゼットを開け、ため息交じりで想夜のドレスを選びなおした。
そんなやりとりをしていると、想夜たちの背中に弱々しい声がかかる。
「ザッパー、だと? なにそれ、超カッコイイ……俺も、使いたいぜ」
銀ちゃん、カッコイイ……鎌田行進曲の階段落ちよろしく虫の息。
一同が狐姫に目を向けると、ヨロヨロと立ち上がる勇姿を見せてくれた。
起き上がる狐姫、想夜と御殿が肩をかす。
「動いたら駄目だよ、傷口ひらいちゃう」
想夜の心配をよそに、「ザッパー、かっけー。使いた~い」と、連呼する狐姫。どこまでも能天気だ。けど想夜が「体力消耗するよ」と忠告すると、「あ、じゃあいいや。いらね」と、狐姫の中のザッパーは低評価に終わった。
「狐姫さんをソファに座らせましょう。想夜、手伝って」
「うん」
御殿と想夜が狐姫をソファまでつれて行く。
「さんきゅ。ここでいいよ」
狐姫はソファに座ると、背中の傷に響かぬよう、ボクサーよろしく前のめりの体勢で落ち着く。
「ふう、薬が効いているようだ。スゲー薬だな」
「妖精界に伝わる特効薬ですよ」
「ああ、あれ? チョーいいよね~、あたしも使ってるよ?」
華生と想夜が笑顔で相槌。2人ともこの薬にはお世話になりっぱなしだったりする。
「――にしても凄い回復力ね。妖獣というのはそんなに優れた細胞を持っているの?」
「はんっ、気合だ気合!」
叶子の手前、狐姫は肩をグルグル回して力拳を作って見せた。ホントはちょっぴり痛い。それでも元気に振舞う。そうすることで陣営を乱さぬようにする。そうすることで皆の不安を拭うのだ。無理をしなければ大丈夫だ、と。
そんな時にインカムから連絡が入る。
『会場内に不審者と思しき者がいる。総員、会場に集合しろ!』
小安の声だった。
想夜たちは互いにうなずき、会場へと向かった。


