3 名も無き委員会
ここは
校内にはホールと呼ばれる広場がある。
天井いっぱいにひろがる天窓。そこから降り注ぐ日光。自然の恵みに照らされた明るい場所。
中央には大理石で作られた円形の噴水設備。泉の音が安堵の波紋となって人々の心にしみ込んでゆく。
売店や食堂などが充実しており、昼休みには食事やら雑談やらで職員と生徒たちが押し寄せ、賑わいを見せる。
コミュニティーエリアとして学園関係者に大人気のスポット。それがホールだ。
所々に設置された観葉植物がちょっとした癒しを与えてくれて皆のウケも良い。
植物とは不思議なものである。眺めているだけで沈んだ心が軽くなる――そう思う人は多い。
ホールを中心に八方に広がる通路から、小、中、高、大学への行き来が可能。そこはターミナル地点でもある。
現在は校内工事中のためパーティションで区切られており、他等部への進入や一部の売店使用が制限されている。
ホールを通らないと到達できない場所も何ヶ所かあり、遠回りをしなくてはならない。いささか面倒くさい時期だ。
利用者が多い通路とは別に、まったく利用されていない通路もあったりする。例えば、中・高等部から直行で行けるのにもに関わらず人々に忘れ去れらた場所のことだ。
ホールの隅、誰も近づかない薄暗い一本の通路。経費削減か節電か、蛍光灯すら外されていて、人々から忘れ去られた寂しい通路。そこをさらに奥まで進み、突き当たりの非常口を抜けると校舎裏にひっそりと建っている存在。
掘っ立て小屋の離れ。
元々は用具置き場。それから体育倉庫、ニワトリ小屋、ころころ変わる。
そこを再利用して人の出入りできるスペースを作った物好きな輩がいるらしい。
土台も敷かず、柱にベニヤ板を打ちつけただけのような造り。隙間風ピューピュー。ボロさなら、どこかのご家庭の犬小屋に負てない。
会議用の長机、パイプ椅子が2つ3つ。それだけで10人も入れば酸欠地獄が待っている。そのくらいこじんまりした部屋だった。
校舎の外にあるもんだから、非常口を出て小屋に入るまでの間、空まで続く吹き抜け開放感がハンパない。
寒空のもと、生徒たちから忘れられた地――そんなヘンピな場所に物好きは営業していた。
要請実行委員会――。
委員会とは名ばかりで、ただのなんちゃって部。つまり同好会である。
部員が規定数に達していないもんだから部費すらもらえないのがトホホである。
部員は2名。
何の酔狂か、部長の物好きさが転じて開業した同好会だ。
『委員会』という名も部長が無理やり生徒会を押し通して、勝手に命名していた。
正確には『要請実行委員会同好会(仮)』だが、めっちゃ長いので最後の何文字かを省いた――ということにしている。部長のちんぷなプライドからか、同好会として見られたくないらしい。それどころか部活動へのランクアップを望んでいる。
――んでもって想夜も『ナントカ同好会』に入部していた。
要請実行委員会。
聞こえだけはカタく偉そうだが、直訳すると『要請を実行する委員会』……の同好会。すなわち便利屋である。
表向きは青春を謳歌する生徒たちをサポートするボランティア団体だ。が、おもしろくない依頼は部長がすべて棄却してしまうので、結果的に依頼のほとんどを想夜が担うことになってしまう。
ちなみに部長は「急な頭痛腹痛生理痛、ならびに親戚のおばさんが急に……ごにょごにょ」でしばらく不在とのこと。
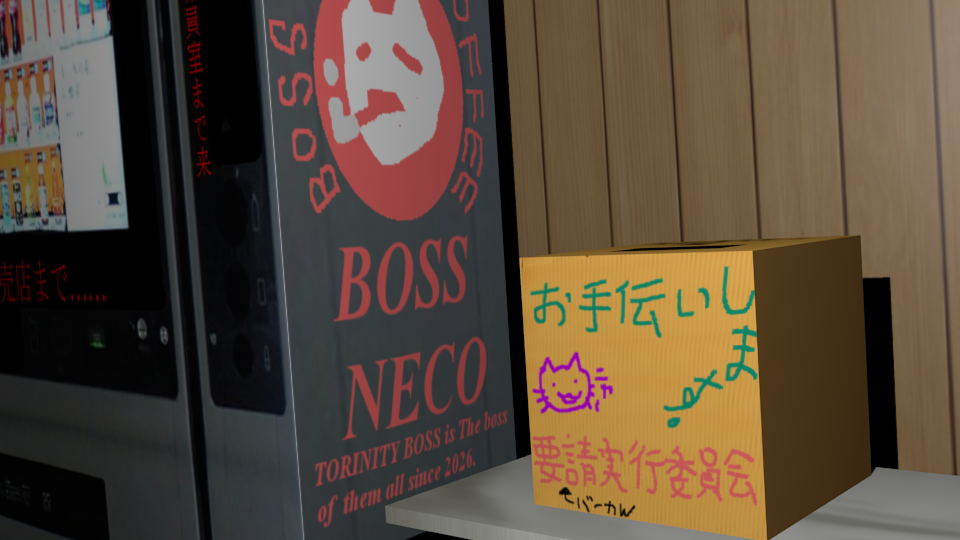
ホールの脇に設置された箱がある。
通称おねだりBOX。主原料はお菓子のダンボール。自動販売機の脇に申し訳なさそうに置いてあるのが痛々しい依頼箱だ。
『お手伝いします。要請実行委員会』
と、箱表面のあちこちにマジックで殴り書きしてある。文字のバランスが崩れ、端っこのほうに進むにつれて小さくなったり折り返したり。けれど製作者の想夜は丁寧に書いたつもりでいる。
どこかの詩人みたいな独特な文字感だが、そこはご愛嬌。象形文字って言われてもいいじゃない、妖精だもの……そをや。
ワンポイントの猫ちゃんが本人のお気に入り。残念なことにイラストのセンスが全然なく、猫だか豚だかわからない。よりわかり易くするためイラストの横に「ニャー」と書いてあるが、「これは猫ですよー、豚じゃないですよー」と、言い訳的な安全策を考慮しているあたりに全米が涙したとかしないとか。
おねだりBOXの使い方はいたって簡単。要請書に内容を記入して入れるべし入れるべし! それで受付は完了、あとは想夜が何とかする。部長は高みの見物。
想夜は部室におねだりBOXを持ち帰り、それをひっくり返して卓上に中身をぶちまけた。
バサバサと机に広がる要請書の束+α。それら一枚一枚に目を通す。
・おねだり1 『別れたカノジョとよりを戻したいの。なんとかしろ、してください。 依頼人:高等部2年 ○岡○子』
・おねだり2 『校庭の雑草、早く何とかしろ! 依頼人:匿名希望』
・おねだり3 『学食安くしろ 依頼人:匿名』
・おねだり4 『お、こんなところにゴミ箱がw』
・おねだり5 『(解読不能の意味のない落書き)』
・例外 レシート。
・ゴミ判定 ペットボトルのキャップ。
想夜は要請書の束とキャップを持ったままワナワナと震えだした。
「ゴミ箱かっ」
怒りMAX。床にペトボキャップを叩きつけた。
カッカッカッ、スコーンッ!
「あイタ!」
カランコロン……
キャップが壁、床、天井で反射して想夜の後頭部を直撃。転がる音が本人を馬鹿にしてるような笑い声に聞こえた。
「もうっ」
こめかみにピクリと浮かんだ青筋がブチ切れそうだった。
依頼内容はいつも似たり寄ったり。ほとんどが匿名希望を名乗り、命令口調であり、暴言だった。使いっパシリもここまでくるとただの殴られ屋である。
おまけに名乗らない生徒からの『ともだち募集』などといった他力本願なものもある。
「友達募集? 自分から声かければいいのに」
悩み事の大きさは大小問わず、要請実行委員会に集まってくる。
散らばった紙の中に目を引くものを一枚発見。
「ん? なにかしら……」
想夜はそれを手に取った。
『雪車町へ。近々転入生くるから~。学校案内すること。あと街も案内すること。先生忙し~から、以上。』
担任からだ。しかもご指名、上から上から。使えるもんは壊れるまで使う。鬼レベルの心意気に敬意を表したい。
「なんかもう、願いするレベルじゃないわよね。先生、これってただの命令文じゃないですか」
肩からサスペンダーがずれ落ち、口元を引きつらせた。
想夜は生徒たちの要請を表にまとめ、おねだりBOXをホールに戻すために小屋を出た。
おねだりBOXを元の場所に戻してホールの食事スペースに向かうと、女子の群れと遭遇する。
くすっ。
すれ違いざま、想夜は笑われた気がした。気になって振り向こうとすると、ひとりの女子に足をかけられ横転する。
すてーん。
「あ痛っ」
狭い廊下に爆笑のノイズが走った。
女子群はおねだりBOXにゴミを投げ捨てると、口汚い言葉を吐いてその場を去っていった。
「えへへ……」
残された想夜は何事もなかったように笑顔を作り、服の汚れをはたいた。
愛宮叶子
ヘアバンドからながれる黒髪のストレートがさらりと揺れ、かき上げる仕草が想夜の目に飛び込んできた。
中央広場の隅っこのテーブルに知った顔――読みかけの本を閉じ、膝の上において天窓を眺めている。
愛宮叶子――学園を運営する愛宮グループのご令嬢。物静かでクールな見かけとは裏腹の、少しおちゃめな性格。力強い瞳、勝気でくっきりとした眉と角度。笑うと少し垂れる切れ長の目が印象的。時折、寂しそうに視線を落とすたびに周囲をざわつかせる。薄幸フェイスでさえ好印象だ。
彼女だけでその場の空気が成り立ってしまう、ひとりで事足りる孤高を謳った存在。コミュニケーション不足というわけではないが、叶子はいつもひとり。
叶子は委員会や部活にも入っておらず、他者との関係もほとんど築かない。
一応、学校関係者なので贔屓沙汰にならぬよう、叶子自ら他者との距離を置いているのだろうと周囲は推測するが真相は誰にもわからない。
理事長の親族であり、問題を起こすこともなかったので教員たちですら物申すことがない。それに、この世で単独行動をとる生徒などめずらしくもない。
ひとりでいる叶子を嫌うものはなく、むしろ好かれる側にあった。手中に収められないのなら、いっそのことひとりでいてくれたほうが嫉妬をせずにすむ。皆、そのほうが気が楽なのだ――そんなアイドル的扱いもされていた。
彼女の素振りや容姿にあこがれて真似をする女生徒もいるけれど、当の本人は興味ないご様子。他者の行動に心が揺らぐことはない。己というものを確立している。
高嶺の花――誰もが持つ、愛宮叶子の印象だ。そして誰もが、叶子に声をかける勇気さえ持っていなかった。
「……」
叶子の唇がなにかを囁くそぶりを見せる。時折、そうやって天窓の向こうに流れる雲を、ひとり見つめては物思いにふけっている。ここ最近、そんな時間が増えた叶子のことを想夜は心配していた。
想夜は気を取り直し、叶子に向かって歩き出す。
「叶ちゃん」
叶子をそう呼ぶのは、叶子からそう呼ぶように言われたからだ。礼儀正しい想夜のこと、出逢った頃は「愛宮先輩」「叶子さん」などと呼んでいたが、叶子は他人行儀を嫌っていた。
想夜は挨拶がわりに手をグーパー。いつものにっこりフェイスで近づいた。
名前を呼ばれた叶子がゆっくりと天窓から視線を落とし、歩いてくる想夜の方を見てニンマリと微笑んだ。
「想夜――」
その後、ゆっくりと視線を天窓に戻した。
いつものヘアバンド。叶子のお気に入り。フリルもなく凝ったデザインでもない、いたってシンプルなもの。どこぞのブランド品ではないけれど、叶子はいつもこれを愛用している。外した後も綺麗に折りたたんではバッグにしまう愛着っぷり。まるで自分の命そのもののように扱うのだ。大事に。それは大事に、大切に――。
「想夜、変わった委員会に入ったってウワサを聞いたのだけれど……頑張ってる?」
「うぐっ」
ニンマリの正体はカウンター攻撃の前フリだったのか、想夜は返す言葉を詰まらせた。委員会も部活も肩書きであって、現状は奴隷といっても過言ではない。
浮いた存在とはいえ叶子は学年主席。優れた頭脳の持ち主で頭もキレる。おねだりBOXのゴミ箱化どころか、想夜の奴隷化さえ以前から察していた。
けれども、どんなことにも懸命に取り組む想夜を応援している側の人間である。入学当初から親身に接してくれる生徒のひとりだ。
人間界に来て右も左もわからない想夜にとっては心強い人脈、大切なお友達。でも、自分が妖精であることを叶子にも打ち明けてはいない。
叶子の住む愛宮邸には何十もの使用人が在籍しており、愛宮はそれを雇うほどの大富豪。
愛宮邸には何度かお招きいただいたことがあったが、敷地内で迷子になったり、新米メイドの不祥事で頭上にタライや水バケツが降ってきたり……と、あまりいい思い出がないのも事実。
そんなトラップ屋敷でも、ご馳走になったケーキは格別だった。思い出しただけでホッペがとろけて落っこちちゃいそう。「ヒャッハー!」と妄想の中、想夜はお菓子の世界で宙を舞う。人間も妖精も甘いものには目がないのは万国共通である。
今ではすっかり愛宮邸の常連だ。菫の園芸のお手伝いのために頻繁に出入りするようにもなっていた。
想夜はハッと我に返りヨダレを拭う。
お菓子の国から帰還し、担任からの要請書を叶子の前でヒラヒラさせて口を尖らせた。
「も~、こんなの入ってたんですよ? 先生ったら人使いがあらいんだから」
妖精だけど……ボソリとひとりツッコミ。大丈夫、誰にも聞こえていない。
「へえ、見せて」
「どうぞ」
紙を手にした叶子がサッとそれに目を通す。
「担任からの依頼ね。転入生の町案内?」
「みたいなの」
訝しげな顔の叶子に対して想夜が答えた。
新しくこの町にやってくる人たちに捧げたいものがある――この学校のこと、この町のこと、この町に住まう人々のこと。それらに好意をいだいてくれたら嬉しい。そう伝えたい。かつて自分を迎え入れてくれた時のように。
人間界に来たばかりの想夜を、叶子はいろいろな場所に連れ出してくれた。
ひとり人間界にきて、不安でいっぱいの想夜。心が折れそうな時もあったけど、そんな想夜に対して贈られた言葉がある。
『ほんのわずかでも望みを捨ててはいけない。それは未来の自分を殺す行為だから』――そう、叶子が言ってくれたのを想夜は決して忘れない。
『未来』とは『今』の積み重ねなんだ。だから人間界での出来事ひとつひとつを大切にしている。
未来に優しい栄養を与えたい。「人間界は素敵な世界だった」と、未来の自分に言ってほしいから。
「こんな時期に転入なんて珍しいですね。先日入学式があったばかりなのに」
と、想夜はテーブルに置かれたフキンを意味なく手にして遊ぶ。
「そう言えば、転入生は2名いらっしゃるって先生方が話してたわね」
叶子の目が何かに思いをめぐらせるよう宙をさまよう。
漆黒とブロンド――叶子の脳裏にふたりの人物が浮かんだ。御殿と狐姫の姿。
叶子は家の都合上、アングラ住人と屋敷の中で顔を合わせることがある。とはいえ、廊下ですれ違う程度のもの。深入りはするつもりはないし興味もなかった。
MAMIYAという場所は、あらゆるところで金と権力のやり取りがおこなわれている。ビジネスは決して綺麗事ばかりではない。泥のついた人間を屋敷に招くことのほうが多い日もある。そんな家柄の娘として、世の中のダーティな部分にもウンザリしていた。ビジネスの闇に慣れてくる自分も大概だ。と叶子は思う。日に日に心が麻痺してくる。笑う者と絶望を抱くものの狭間で、世界とはこんなにも無慈悲なのかと落胆することがある。
人の面を被った魔物は一般人のすぐ横にいる。いいように利用されないためにも、心に鉄板くらいは装備しておきたい。それでも防御がたりないくらい用心が必要な世界――叶子はそれを垣間見てきた。
心の隙と傷口はよく似ている。えぐられたら最後、地獄のような痛みが待っている。
叶子の冷めた一面もそんなところから芽生えている。屋敷に訪れる常人離れした下衆な輩など珍しくもなかった。
――しかし、である。
せんじつ愛宮邸を訪れたふたりは、今までに感じたことのない違和感があった。
黒髪と金髪、ふたりのどちらのことを言っているのか?
そう問われるならば「どちらも」だが、強いて言うなら咲羅真御殿という黒髪の人物だ――。
叶子は御殿を思い浮かべた。
顔の若さから推測して自分と同年代か年上だろうと踏んでいる。落ち着きある表情や物腰など、クールな素振りを見せる叶子といい勝負だった。あれだけ落ち着いた同年代がいるのだろうか? いや、きっと自分と同じように若くして闇の部分を見たことがあるのかもしれない。傷つかぬよう、心に鉄の鎧をまとっているのだと理解する。
(高すぎない鼻や髪質からして東洋人であることには違いないわね。日本語の発音に違和感がないから恐らくは日本人。愛宮邸では英語も流暢にネイティブしていた。いったい何者?)
叶子の中で御殿は『できる女』として位置づけられている。
特に興味を引いたのは御殿の黒い瞳である。死者のように考えが読めないようでいて、死んだ魚の目のそれとも違う。例えて言うならば、地獄の深淵で無表情のまま月見をしている天使。羽ばたけるのにもかかわらず、地にとどまり続けているような、血に飢えた、そんな冷めた瞳。
(地獄で誰かと待ち合わせでもしているのかしら? 物分りのよい大人を演じていながらも聞き分けがなくて、親に叱られベソかく子供――咲羅真御殿。大人なのか子供なのかさえも分からないわ。美人で力強い、女神のようなしなやかな肉体を持ったマッチョ? はあ、もう……性別の概念すら壊れそうね)
叶子はそうやって想定外の存在に苦笑した。
叶子の中ではいっこうに御殿の人物像が定まらず、思考は放浪するばかり。年齢、性別、国籍、すべてがチグハグ。ピタリとこない。
考えれば考えるほど、例えるなら例えるほど矛盾だらけの存在。それが叶子が抱く御殿の印象。まるで漆黒の亡霊だ。
叶子は己を勘ぐる。
(パートナーのブロンドにすら心を開いていないと感じるのは気のせいかしら? マンネリ化したカップルじゃあるまいし)
御殿の落ちついた物腰の裏側に感じる執拗な壁。礼儀正しいのは結構だが、他人行儀も度を越えるとただの人間不信だ――友の名に『様』をつける奴などいないように。
咲羅真御殿は簡単に人を信じないアングラ人間なのだと、ひとり納得する叶子。
(こんなにも他人のことを考えるのは想夜と出逢ったとき以来ね)
叶子にとっては想夜も御殿と同様、不思議な存在だった。もっとも想夜の場合、素直で礼儀正しく天真爛漫の可愛い珍獣に見えたので興味をそそられたのが理由だ。
(私は変わったものに興味を抱くタイプのようね)
ひとり納得する叶子だった。
叶子が考えをめぐらせていると、想夜が顔を覗かせてきた。
「叶ちゃん、相席いーい?」
「いいわよ」
「わーい」
想夜が叶子の隣に腰を下ろした。そのあと三角パックにストローをブスリと刺し、
「ちゅううううううううううううううううううううう~」
おもむろに中身をチューチュー吸い始めた。若者らしい見事な吸いっぷり。スッポン想夜、ここにあり。
スッポン想夜、お次はパンの袋をあけてがっつく。
「うん、うん。今日もMAMIYAのパンおいひー」
リスのようにほっぺを膨らませ、体を左右に揺らしてリズムをとる。
「そう? ふふふ、ありがとう。ソースついてるわよ」
口のまわりについたソースを叶子が指摘し、想夜に紙ナプキンを差し出した。
売店にならぶパンもMAMIYAの経営する食品工場から出荷される。一部の商品は愛宮邸の厨房で作られており、数量限定の貴重品。味も然ることながら低価格もウリだった。なので、われ先にと群がる野獣がホールでバトる日々である。
想夜もその野獣の中の一匹――妖精だからってナメてかかるとヤケドするぜぃ、ランチタイムは弱肉強食、心はいつもハードボイルド。校舎というサバンナを駆け抜け、食堂という名の戦場で野獣を演じきるのさ、キリッ。
微笑む叶子の目が想夜の手をとらえる。パンを握るその手は傷だらけ。擦りむいたであろう生傷が痛々しく目立っている。昨夜の一戦で暴魔の打撃によりアスファルトを転がり、ビルに叩きつけられた時にできたもの。
傷を見た叶子がクスリと笑う。
「お弁当作りに挑戦したけど、包丁さんにやめとけって言われた?」
「ブフォッ!」
口に含んだジュースを吹き出した。危うく叶子に顔面シャワーをあびせてるところだ。ウィットに富んだシャレでさえも、叶子の育ちのよさが感じられる。が、いくらなんでも公共の場で顔射は失礼である。
ゲホゲホとむせる想夜の背中を叶子がさする。
「ち、違っ。近所のノラ猫と、戦ってた、のっ。魚泥棒なんとかしろ! ……っていう要請がきちゃって……げほっ」
むせながらしゃべり、ズズズとストローを吸ってはぐらかした。
敵に吹っ飛ばされてビルにめり込みました。当方13歳、独身、妖精――とは言えまいて。
半笑いで2つ目のパンをほおばる想夜。そのパンをドヤッ! と叶子に見せつけた。
「じゃじゃ~ん☆ 伝説の聖色サンド、ゲットしました! 叶ちゃんも半分食べる?」
あまりの人気っぷりで、なかなか買えない幻のMAMIYA賄いサンド。
想夜はそれを半分ぎって叶子に差し出した。
「はい、半分こっ」
満面の笑みで聖色サンドを半分さしだす想夜。幸せをまわりの人と分かち合う性格。
差し出されたパンをまじまじと見つめる叶子。
かつては賄い食で影薄だったメニューでさえ、今ではご当地グルメに匹敵する。
聖色サンド目当てに、一体どれだけの血が流れたことだろう。しみじみ……。
つい先ほど、叶子がホールに来た際、売店は生徒たちでごった返していた。
学園の非公式ルールブック。その一説によると、人ゴミから叩き出された軟弱者は、獲物ゲットに失敗したルーザードッグ。聖色サンドを味わう資格すらない、らしい。
生徒の中にはチームを組んで挑む輩も出はじめる。影の専門家たちはそれをチームバトルモードと称した。
伝説から神話へ。神話からお笑いへ――明日も骨肉の争いは続く。
想夜の力説を聞き入る叶子。
「叶ちゃんもバトる? 明日もあるよ。チーム組もうよ」
「参戦する気はないけど考えておくわ」
叶子は遠まわしに拒否した。
「想夜はさっきまであの群れの中に?」
「いました」
キリッ。
「でも、いつも弾き飛ばされちゃうんだよね~」
「ルーザードッグ認定で淘汰されたわけね」
たはは、眉を緩める想夜が子猫のように弱々しく肩をすくめる。叶子もそれに習った。
ふたりはパンをほおばる。
ふたたび叶子は天窓を見つめて遠い目を作り、
「淘汰、か……」
ポツリと呟く。
「ねえ想夜」
「ひゃい?」
もぐもぐ、ズズズッ~。想夜が口の中のパンをジュースで流し込む。
「外国より遠い国って、どこにあるんだろうね……」
叶子が問うも、想夜はパンが胸につかえて目を白黒させている。どうやら慌てて食べ過ぎたようだ。胸を叩いて、やっとこさ喉の通りを良くする。
「へ? 叶ちゃん、なにか言った?」
もう一度、パックをズズズゥ~と吸い込むスッポン想夜。
叶子は力なく微笑んで首を横に振った。
「ううん、なんでもない」
そう言って、ふたたび天窓からそそぐ光を見つめていた。
叶子は遠く、遠く。雲の向こうの、あの彼方を見つめ続けた――。
妖精界の授業
教室内――。
あたし、雪車町想夜の席は窓際にあります。
叶ちゃんとのお昼を終えた後のこと。午後の授業中、窓の向こうに流れる空を眺めていました。
快晴。どこまでも広がる空。いつもの光景――ふと故郷を思い出しました。
妖精界の学校――授業の基本はノートと筆記魔法。羽ペンから放出される記述光でノートの行をなぞって書き込む方法が主流です。文字消去も消しゴムは使いません。ペンの羽でサッとこすれば消えます。紙は貴重な物資であり、とても高価なものなの。それ一冊で人間界のゲーム機本体が買えるくらいです。
資源は有限。そのことを妖精たちは知っています。
学校でノートに記録した授業内容を家に持ち帰り、自室にある四角形の平たい水晶にデータを転送する。そんなやり方が妖精界では一般的です。
学校から直接、自分の部屋の水晶にデータ転送することも可能だけれど、学校所有の水晶サーバーに負荷がかかるため、これをやると先生に怒られちゃう。
サイバーシステムを使わない妖精界での生活はアナログだと言われても間違いはないのですが、魔力の存在がその言葉をしりぞけます。高度なサイバー技術も魔術も、同じ力であることに変わりはないからです。魔力はこちらの世界のデジタルに匹敵します。
2034年現在。人間界の授業はどうでしょうか?
目の前にはディスプレイ化された黒板、半透明のガラス状の机。そこには教科書のデータが映し出されています。あたしたち生徒は各々が端末を所持し、人工知能が教師と生徒のサポートをしてくれます。
はじめてディスプレイ化した黒板や机を見た時、「なんじゃこりゃあ!」と派手に驚いちゃった。だって魔術を使わずにこんな高度なことができるんだもの。人間ってすごく頭がいいんですね。
魔術を使わずしてデータのやり取りをおこなうシステム。当時のあたしときたらサイバー化された現代社会にタイムスリップしてきた原始人。見るものすべてが新鮮でした。
だけど、慣れとは恐ろしいものです。妖精界と人間界は似てる部分が多いため、原動力が魔法か電気かという違いだけに気づきました。あたしが人間界の常識に染まるのには時間がかからなかったわけです。
授業は知識の宝庫だけれど、先生がこれでもかと言わんばかりに頭に詰め込んでくるのには骨が折れます。なんといいましょうか、好きなお菓子を無理やり口いっぱいに押し込まれている感じがして、まるで拷問です。
幸い知識にはカロリーがありません。なので太りません。カロリーゼロは女子の救いです。
人間界の知識にはとても興味があります。授業中でもそれ以外の場所でも、妖精界と違うところには真っ先に目と耳がいきます。みんなからは好奇心旺盛だとよく言われます。
人間界に来る前、あたしなりに人間の基礎知識を詰め込んできたつもりだけれど、百聞は一見にしかず。やっぱり驚かされることが多くて、覚えなきゃいけない情報が山ほどありました。
図書室は知識の宝庫、よく本を借りて寮の自室で読んでます。すっかり常連と化して、図書委員さんにも顔を覚えてもらいました。現在のお気に入りは歴史学全般。なんてったって人間界の歴史が記されているのだから興味がわかないわけがありません。
先生からは「雪車町はまじめかつ勉強熱心だ。成績はクラスで2番か3番かをキープしているし学年では10位以内。1番にならずとも比較的上をキープしているな。だが調理実習だけはなんとかならんものか。そのままだと死人が出るぞ?」とよく言われます。お酢で煮物を煮込んだのがよくなかったのね。料理できる人はきっと天才か何かなんだわっ。
人間界での調べ物で徹夜した朝、目を真っ赤にして遅刻したことが何度かあります。それだけ人間界の学びは大好き。日本に侍や忍者がいないのはガッカリでしたが、テレビ番組でエレキベースを持った侍が出てきたので感動したのは覚えてます。日本の侍って楽器も演奏できるのね、すごいことだわ!
ベースをかき鳴らしてダメ出し毒舌悪態を言ったあと「無念!」と嘆き、最後のシメに自虐ネタで「介錯!」と叫ぶ姿に日本魂を感じます。
あたしは妖精だけど普通の女の子です。解せない授業も珍しくありません。
例えば忘れもしない現国のテスト。問題の中で『この時の作者の気持ちを20文字以内で表せ』という内容。
(作者の気持ちなんて作者本人にしか分からないのに……)
テスト中に固まりましが、いや待てよ? と深く追求します。
(現国の授業を通して相手の考えを盗み取る問題……とか?)
この世界では超能力者の育成にも力を入れてるんだと本気で考えたことがありましたが、先生が考えた理不尽な問題だと先日理解しました。人間界で生きてゆくのも大変です。
授業終了のチャイムと同時に、あたしは職員室に呼び出されました。
教室から出て行く時、同級生の子がニヤニヤしながら近づいてきました。
「雪車町ぃ、なんかやったのぉ~?」
「なにもやってないと思うんだけど……」
心当たりがまったくありません。
ニヤつく同級生の態度。それに良い印象は持てませんでした。
あたしは誰かの悪口や陰口に参加しないためか、教室でも浮いた存在のようです。でもそれはあたしの正義に反すること。参加しなくてもよいことなので、胸を張るべきだと思います。
教室を出てゆくあたしの背中に笑い声が集中しました。
あたしは、それでも振り向かない。ガマンしてやり過ごせばそれでいい。
何も、言わないんだ――。
職員室に呼ばれた理由は2つありました。一つはおねだりBOXに料金表が張らていたこと。これが職員の間で問題となっていたようです。もちろん誰かのイタズラなので必死の弁解。いつものこと、いつものこと……。
もう一つは担任の女性教師からの依頼です。それは例の要請書の内容でした。そうです、叶ちゃんに見せた要請書のことです。
「
「社宅だったマンションだよ」
細い道を入ったところにある建物ですか?」
「そうそう、あそこな。じゃ、よろしくぅー」
先生はなかば投げやり。でも町の案内役だなんてとっても魅力を感じるわっ。
よぉーし、要請実行委員会の出番ねっ。あたしは転入生の住所が書かれた紙を片手に校舎を後にした――。
赤帽子
想夜がちょうど昇降口を出ようとした時だ。その足がピタリと止まる。
「あれは……」
メイド服に身を包んだひとりの少女が目に入り、とっさに物陰に身を隠す。目の前にいるのは、深夜の戦闘で助けた少女だった。
「やっぱり愛宮邸の人だったのね。あの時は真夜中だったから暗くてよく見えなかったけど、こうして目を凝らしてみると美人さんなんだぁ。肌とかとってもきれい。まるでお人形さんみたいだわ」
一見、その辺にいる10代の少女と変わらないものの、人間離れした透明感あふれる肌。風に逆らわない流れるようなミルクティー色の長い髪。それをシニヨン風にまとめて仕事モード。魅力的だが独特な違和感を醸し出す真っ赤な瞳――それらは人間の体では決して表現できない。
自然に溶け込むような容姿は想夜と似てる雰囲気が多く、妖精界の懐かしい香りを感じてどこかホッとする。
「でもあの人の顔、以前どこかで見たことあるような……」
頭の中で何かが引っかかり、ポケットから小さめの六角水晶を取り出して詠唱。指先を忙しなく動かすと、かすかな光を放つ文字列が浮かび上がり、5インチほどの半透明モニターを作り出した。ハイヤー技術の結晶である。
「えーと……」
サッサッ、ゆびきたす、ゆびきたす。
「これじゃないし、このデータでもない……」
さらに指先を動かし、モニター内に映し出されたデータをテンポよく切りかえる。
想夜が操作しているのは水晶端末――妖精界では水晶端末と呼ばれている通信端末がある。人間界ではモバイル端末がそれにあたる。フェアリーフォースと会話をしたり情報検索したりできる便利ツールだ。
水晶端末の仕組みは、電気代わりにユーザーのエーテルを消費して妖精界の水晶ターミナルにアクセス。その後、水晶サーバー内のデータベースを閲覧できる。想夜は権限が低いために最小限の情報しか見られないが、ひよっこ軍人を支えるだけの機能は備わっている。
エーテルバランサーの想夜には閲覧権限があり、一番低いレベル1の機密情報を知ることができる。
レベル1の閲覧項目は以下のとおり。
①ハイヤースペック発動者リスト
②ハイヤースペクターリスト
③逃亡者リスト
発動者とハイヤースペクター――ハイヤースペックを所持した妖精と人間を指す。それが項目①と②。
逃亡者――何らかの問題があって、妖精界から人間界へ逃亡をした者を指す。それが項目③。
人間界にやってきた妖精の中には、さまざまな逃亡者がいる。事件を犯して逃亡する者や、やんごとなき事情で逃亡を図る者まで様々だ。なかでも厄介なのが『妖精兵器ディルファー』の存在だった。
『妖精兵器ディルファー』――その昔、ゴブリン族が大規模なクーデターを起こした時のこと。暴動の最中、妖精界に一匹の兵器が放たれた。
桁外れの力を持った特殊な存在、最狂最悪のゴブリン。それが妖精兵器ディルファーだ。
ディルファーはひとりの人間との接続に成功し、ハイヤースペクターとなった人間と共にハイヤースペックを発動させた。妖精界が地獄に変貌を遂げた瞬間だった。
――この氾濫がフェアリーフォースとゴブリン族との戦争を招き、妖精界は世界の半分を失った。
こうして妖精界は滅亡の危機に直面する。それほどに最悪のインパクトをあたえる妖精だった。
ディルファーは戦乱後、禍々しい羽を広げて人間界に逃亡したといわれている。現在、妖精界全域で対策が練られ、フェアリーフォースが血眼になって捜索している。
そんなディルファーという脅威。当然、想夜の力では手に負えるはずもなく、見つけたら逃げるのが精一杯。なのでエンカウントは是が非でも避けたいと常日頃から思っていた。生きて逃げられる保障がない。まさに恐怖の塊である。
想夜はディルファーに縁のないヘタレバランサーだけど、それ以外の雑用は自分の身の丈に合ったチョイスだと感じていた。いい意味で謙虚だし、悪い意味では自己評価が低い子。
ここで水晶端末を操作する手が止まる。
「発動者は……誰もいないわ。リストは空白ね」
リスト登録はターゲットの所在確認後に記録されるので、確認が取れない場合は未登録となっている。
想夜はふたたび手を動かした。
現在、この地域での発動者・所有者は確認されていない。しかし逃亡者記録は違っていた。
「……ん? お? おおう!?」
モニターに少女の顔写真が映された、と同時に想夜の目がまん丸になる。無言のまま、写真と目の前のメイドを交互に見くらべた。
「――間違いないわ。あの子……逃亡者だ」
想夜はモニター内の少女の名を調べたが、期待を裏切る結果に終わる。
『権限がないため閲覧不可』
想夜はぽかんと口をあけた。
「一体どうなっているの? 名前すら確認できない逃亡者だなんて」
モニターに映っている少女と昇降口の少女の顔は一致している。だというのに、名前すら分からない。
想夜はため息を洩らした。
愛妃家女学園 第3女子寮――そこが想夜の住居である。
通常はふたりで一部屋を使用するのだが、今のところ想夜と部屋をともにするものはいない。部屋を独占できるが、ちょっぴり寂しい。
こちらへの入居が決まったのは人間界に来る直前のこと。手配してくれたのは菫だった。愛宮の特権といったところだろう。菫は礼儀正しい想夜のことをえらく気に入ってくれたようで、あれこれ世話をやいてくれる。とうぜん想夜が妖精であることは知らされていないが、叶子同様、想夜のことを気にかけてくれるひとりだった。
部屋はいたってシンプル。ベッドとタンスと勉強机。妖精界から持ってきたきた得体の知れない植物が小さな鉢に植えてあり、小さな花を咲かせている。
手ごろな大きさの立てかけ鏡。小物入れには髪を結うためのリボンやシュシュ。変なキャラのキーホルダーも混ざってたりするあたりが今どきの女の子女の子している。
テーブルの上にはカップに注がれた飲みかけのミルクティーと少し大きめの水晶。携帯用の水晶端末よりも多くのデータベースにアクセスができるので、細かい情報収集には重宝する。裏を返せば、わざわざ部屋に戻らないと使えないのが難点だ。
妖精界からの逃亡者は確保後、強制帰界させる。逃亡者の居場所を本部に通報するのもエーテルバランサーの役目だ。
妖精界には特別な犯罪者を取り締まる組織も存在し、想夜たちエーテルバランサーが通報後、確保部隊が人間界に送り込まれる。
フェアリーフォースは妖精界を守る正義の組織だ。そこへの正式入隊が想夜の進路。
「将来は悪者をバッタバッタと投げ飛ばして、平和な妖精界をとりもどすんだから♪」
振り上げた拳に力が入る。エーテルバランサーになった理由の1つは世界平和だ。
「でも不思議ね。逃亡者がなんで叶ちゃん家で働いてるんだろう?」
光あれば影もあったりなかったり。メイド逃亡者は使用人となって愛宮邸に籍を置いていた。つまり人間として生活している。
「しかも叶ちゃん家で」
サスペンスのお約束、犯人は身近な人でした。灯台もと暗し。
迷探偵想夜は愛宮メイドの事をあれこれ推理する……が、すぐに飽きた。
「んん~っ。帰宅してからずっと部屋にこもっているわね」
座ったまま両手をあげて体をピンと伸ばし、後ろのクッションに倒れた。その振動でベッドの上に放置していたティーンズ誌が頭に落下して直撃。
バサバサっ。
「あうちっ」
あまり痛さに転げまわる。
「あ~も~! いつも叶ちゃん家にお邪魔してるのにぃ~、全っ然気づかなかったよ~。自分の洞察力の無さには幻滅ね」
クッションに顔をしずめ、足をバタバタさせて悔しがる。
逃亡者は様々だ。人間に溶け込んで普通に暮らす者。人間界で私欲をむさぼる者――何にせよ、界外逃亡は過去のやましさからの結果というのが世間の考えだ。
逃亡者には狩る者が必須。だからエーテルバランサーが生まれるのも必然である。
犯罪者を帰界させればフェアリーフォースからの評価も高い。そんなことから想夜は自分の行いが平和に貢献できると信じている。
身を起こし、不思議そうに水晶モニターをのぞきこんだ。
「逃亡者について少しだけ書かれているわね。『特定秘密保護データの情報漏洩』……なんか難しそう。この子、一体何をしたんだろう?」
何度もデータを閲覧してみたが、名前はおろかそれ以上の詳細が記されていない。情報が不足しており、未登録の項目が多い。
想夜は撫でるように指を動かし、水晶内のデータを切り替えてゆく。その姿はタッチパネルを操作する人間そのもの。
名のなき逃亡者だが、気になる点をいくつか見つけた。
――『ハイヤースペック・ネイキッドブレイド』
「ハイヤースペック・ネイキッドブレイド……? え~と、ねいきっどぶれいど、とは、なにか? 助けてグルグル先生~、おりゃ!」
検索ボタン、ポチっとな。
妖精界の検索サイトグルグルで詳細を調べてみる。「聞く人いなきゃ、グルグれカス!」が合言葉。
「あ、ヒットしたわ。どれどれ……」
ネイキッドブレイド――『2本の刃を操る能力。片刃のカッタータイプ。長く、広く、平たい、薄型のブレイドを作り出す能力。爪が進化したもの。装甲は非常に硬く、撫でるだけでも充分な切れ味を発揮する。本来は二刀流として使う。またはこれら2本をつなげて1本にすることで、長いギロチンブレイドとしても使用可能』
使用種族:赤帽子――。
「この写真と説明にはカッターナイフ状の刃で大きさは1.2メートル、幅約8センチ、太さ5ミリ未満って書いてある。文房具のカッターを拡大したような形状ね。それを2本も生み出す妖精、赤帽子か。2本の刃はハイヤースペックだから、とうぜん能力を人間に託すことができるわね。それを使用する人間は赤帽子本人が使用するよりも強力なネイキッドブレイドを使いこなすことができるはずよね」
想夜はもう一度、メイド服を思い出す。
「赤帽子……そうか、だからあんなに赤い目をしていたのね」
ルビーのような赤い瞳が想夜の脳裏をよぎる。
赤帽子は鋭い爪で何でも切り裂く妖精だ。気性は極めて残忍で狂気に満ちている。人々の悲鳴が好きでたまらないのも特徴だ。連続怪奇殺人犯にはこの手の輩が多い。
――そんなことを思い出してガクガク身震いする。出来ることならお近づきになりたくないのだが、身近にいる以上、尻込みなんてしていられない。
先ほど奇襲をかけてきたティーンズ雑誌の週末占いが目に入る。
『今週のあなたの運勢――チャンバラ注意。長さも大きさも届かず敗北。残念……』
想夜の顔から一気に血の気が引いた。
とはいえ、下校時に目にした赤帽子メイドの表情からは残虐性のカケラも見受けられなかった。それどころか、おっとりしている表情に見え隠れする寂しげな雰囲気が、人間界で孤独に戦う想夜には好感が持てたほどだ。
想夜は意を決して立ち上がった。勢いづいて屈伸を数回。
「うん、捜査の基本は足だわ! あイタッ」
膝がピキッと変な音を立てた。
「現場100回。情報収集。それじゃあ出撃しますか!」
さっそく調査に取りかかろうとした時だった。メールが入ったので確認する。
『ちゃんと街案内しとけよ by ユア・ティーチャー』
――はて? 何か忘れている気が。
そこでテーブルの上に置いた紙切れに目いく。続いて時計を見て仰天。
「……大変だわ、もうこんな時間。調査はひとまず後回しね」
それでいいのか公務員。
教師からの催促メールを受け取った想夜は、急いで寮から飛び出した。
駅からから伸びる小さな国道。それに沿って目的地へと向かう想夜。
転入生には「案内役の生徒を向かわせる」との連絡が学校側から伝わっているらしく、想夜が転入生の家に訪問することになっていた。まったくもって人使いのあらい担任である。
下校前に渡された紙を取り出し、簡単に書かれた地図を見てホッとしたのはつい先ほどのこと。
「
女子寮、愛妃家女学園、転入生のマンションがある濡笑エリア。これらを線で結ぶと正三角形になる。その中央に愛宮邸が位置する。
想夜が地図を片手に駅前をトボトボ歩いていると、反対側から知った顔がやってきた。
「あ、叶ちゃんだ! おーい!」
いつものクセで大手を振って声を上げてしまい、無関係な通行人まで振り返らせてしまう。しかも大きく挙手していたので『わたしが犯人です』と言わんばかりの醜態っぷり。
プークスクス。
笑いの的――視線の弾幕が痛い。
向こうのほうで人混みに混じった叶子もクスクス笑っている。
想夜は恥ずかしさのあまり赤面。背中を丸め、コソコソと叶子の懐にもぐりこむよう近づいた。
最初に話しを切り出したのは叶子からだ。
「想夜、転入生のとこ行くんでしょ? 私も付き合うわ」
「え、いいの?」
「ええ。私も転入生に渡したいものがあるの」
叶子は笑顔で頷き、手にした紙袋を開いて見せた。
「うわぁ、いい香り。何が入っているの?」
想夜が中を覗き込むと、色とりどりの焼きたてパンが詰まっていた。甘い香りがあたりに漂い、食欲を刺激してくる。
「お屋敷の者から預かってきたの。想夜の分もあるからみんなで食べましょう」
嬉しいお誘いに尻尾を振る想夜。
「叶ちゃん、家に帰ってからここに来たの?」
「ううん、下校中。これから帰るところよ」
「ふ~ん……あっ」
想夜は昇降口に立っていた赤帽子の少女を思い出した。
(きっとあの子、叶ちゃんにパンを渡すためにやってきたのね)
そう理解した。
(ということは、まさか……)
想夜は忍び込んだ猫のようにノソリノソリと首を動かし、あたりをキョロキョロ見回した。
警戒モード実行中(※ただのビビリモード)。
(……誰もいない、みたいね)
メイドの赤帽子。その姿はどこにもなかった。
「ね、ねえ叶ちゃん」
「ん?」
「あの、こう……なんてゆーの? こんなふうに眉がおっとりしてて、髪がこんな感じのストレートでミルクティー色で、それがシニヨンで、目が赤いメイドさんは来てないの?」
サッサッサッ、リボンを解いて身振り手振りで忙しい。名前が分からないだけで苦労はひとしお。ゼスチャー機能は体力をはげしく消耗させる。
「ふふっ、うまいうまい」
あまりのおかしさに吹き出す叶子。よほどゼスチャーがおかしかったのか、笑い涙を指で拭っている。
「きっと
「ケーキ?」
あらま、おいしそうな名前。とうぜん想夜は甘いスポンジお菓子を想像する。
息切れ想夜は、ほどいたリボンをせっせと結ぶ。叶子もリボン結びを手伝う。
「九条華生。仕事中だったけれど、わざわざ学校に寄ってパンを届けてくれたの。リボン曲がっているわ」
「あ、ありがとう」
(ふむ、九条華生さんっていうのか。華生さんが妖精だということを叶ちゃんは知っているのかしら? ううん、知っているはずないわ。だって一般人が妖精の存在を知れば大騒ぎになるもの)
愛宮メイドとして暮らしている理由も気になる――想夜の疑問は尽きない。
(焦って大事になってもマズイわ。けれど叶ちゃんの身にもしものことがあったら――)
赤帽子は残忍な性格の種族であるため、タチの悪い敵の可能性が高い。最悪の場合、必要以上の血を見る戦いも念頭に入れておく。
勘ぐりすぎても変に思われるので、想夜は平然を装った。
「メイドさんのお仕事って大変?」
「普通だと思うわよ。何なら、うちでバイトする?」
「時給は?」
「720円」
安っ。
(で、でもバランサーより高いわね。心が揺らいじゃう)
揺らいじゃダメだろ。
そんなこんなで叶子と共に『ほわいとはうす』に向かった。
『ほわいとはうす』へようこそ。
御殿と狐姫は濡笑エリアを訪れた。
国道からはずれて小道に入り、人通りの少ない道を1~2分歩くと車1台が通れるほどの狭い路地がある。車がビュンビュン行きかう大通りとは違い、うるさい無数のエンジン音とは無縁の住宅街。
――そんな静かな場所に小さなマンションはあった。

「……ここね」
御殿が不動産屋から手渡されたメモと建物を交互に見比べている。
入口のステンレス製アーチにデカデカと『ほわいとはうす』と書かれたプレートがかかっており、「この物件がそうですが何か?」と、建物自体がドヤ顔で主張していた。
築20年。鉄筋の建物はいたってシンプルなつくり。タイル張りした外壁、5階建て。玄関通路は外作り。ドアを開ければ目の前に空が広がっていて開放感がある。
狐姫が建物を見上げた。
「ほわいと、はうす? ここが? うへぇ、名前負けにもほどがあるだろ」
ついアメリカの白い家と比べてしまう。
狐姫の率直な意見に対し、御殿はあえてノーコメント。雨風しのげるならそれでいい。聖色市の滞在期間は短いと予測していた。
「アメリカの某家は銀幕の中で宇宙人やらテロリストやらに爆破されまくってたよな」
「そうならないことを願うわ」
ふたりは建物の無事を祈った。
ほわいとはうす。基本、社宅として貸し出しているマンションらしいが、民族大移動と化した社員たちの引越しもあり、満室だった建物に空きができた。
不動産屋から鍵を預かる時に「住人はほとんどいない」と聞かされている。そんな理由もあり、愛妃家女学園から近い場所に住居を確保できたわけだ。
「学校にも愛宮邸にも近いし、幸運ね」
「どうせなら学校前のマンションのほうが楽でいいじゃん。あっちはジャグジーとかあるんだろ?」
「2LDKもあるんだから贅沢を言わない。ちゃんとふたり分、部屋も用意してあるから」
学校も駅も歩いていける距離にある。ここは最高の秘密基地。
アーチを潜り抜けて石畳を渡りながら、雑草の入り混じった芝生に目をやる。
「そろそろ雑草、ヤバくね? 膝まで伸びてんじゃん」
「掃除は管理人さんが定期的にやってるそうよ。夏前には除草するらしいけど、それまでに依頼を済ませてここを出る予定だから気にしなくても大丈夫でしょう」
「おう、ちゃっちゃと済ませて町を出ようぜ!」
建物入り口のガラス扉を開けて、涼風が抜けるエントランスに入る。そのままエレベーターで上がり、3階にある自分たちの部屋へと向かった。
ふたりが玄関の戸を開けて中に入る。
廊下を抜けると明るめのウッディ調フローリングが目の前に広がり、御殿と狐姫を迎え入れた。
「うはぁ~、見ろよ御殿! けっこう広いんだな!」
狐姫がブーツを脱ぎ捨て飛び込んだ。
玄関には先に送っておいた数個の引越し用ダンボールが置かれており、ふたりの着替えや狐姫のゲーム機といった必要最小限のものが詰め込んである。もっとも、玩具系は狐姫が暇つぶし用に詰め込んだもの。人間の子供が好むような俗世的な遊びを愛しているらしく、獣人であるにも関わらず人間人間している。
まだふたりが出会って間もない頃の話。御殿は狐姫に一つ一つ、人間の生活を教えた。テレビゲームはその知識の中の一つだ。
高度な文明を遊びに用いるのは地球上で唯一人間だけ。それは人間界が平和である証ともいえる。万人が兵器に力を注がず玩具に力を注ぐ行為は、一見どうしようもない事に力を使っているようでいて世界の安全を認識させる行為でもある。
力を誤用しなければ、世界が炎に包まれることはない――そうやって御殿は狐姫に語ったことがあった。
けれども狐姫にはそんなことどうでもよいのだ。ただ与えられたオモチャに対して永遠と執着するのみ。
なぜゲームをするのか?
そう聞かれて「そこにゲームがあるから」と返すような感覚に等しい。つまりは平和を意味している。よって勇者狐姫のレベル上げは今日も続く。
人間の歌もよく聴いている。スピード感あふれる8ビートの洋楽ロックは大好物。ポップもパンクもヘビメタもOK。ヘッドホンから「デケデケドンツク!」と音が漏れ出している時は人の話を聞いてない、まったく聞いてない。
なぜ人の話を聞かないの? そこにロックがあるからさ。ライブハウス武道館へようこそ! せんきゅー♪
御殿がカウンターキッチンに向かう。
「日当たり良好ね」
引越し経験者ならばわかるであろう。誰しもその場では冒険家、初めてのマイルームは未知なる世界。
そんな小さい世界を探検する冒険家がここにもいた。
広さ12畳ほどのリビングを見渡す。生活家電一式は全てそろっており、余計な荷物を気にせず引っ越すことができた。
バス、トイレは必須だった。
女子校での生活をするにあたっての問題点は、御殿が男ということだけでない。二足歩行の獣までもがTシャツ姿で寮内を歩き回ってるのを誰かに目撃されたらマスコミの餌食である。
宗盛曰く、女子寮は部屋にバスとトイレがあるとのことだが、いざという時もふまえ、御殿は冷や汗まみれで丁重にお断りした。
殿方の矛先を濡らすことができるほどのふくよかな乳房をぶら下げてはいるものの、同時に世の女性たちを濡らすことができる機能まで下半身に装備しているのだ。たとえそれが立派なモノであれお粗末なモノであれ、バレたら退学では済まされない。三面記事の笑いものである。
数々の問題のクリアをしたのが今回の物件。用意してくれたのは御殿が所属する調査会社の社長。部下によりよい職場環境を提供してくれる出来た社長である。
仕事のしやすい環境を社員に与えるのは法的に義務付けられているし、仕事の効率があがることで、会社の利益上昇にもつながってゆくのが世の常。ブラック企業はその逆である。
御殿の職場の上下関係はよい見本だった。上は下を可愛がり、下は上を慕う。そんな理由もあり、時として残虐な戦場に身を委ねようとも、御殿は会社に貢献できるのだ。
「♪~」
御殿は鼻歌まじりでキッチンを吟味している。表情には出さないが、心の中では遠慮がちのガッツポーズを作ってる。
システム制御でもなく電気コンロでもなくガスコンロ。火力も然ることながら、微妙な調節も可能なあたりが御殿の料理人魂をくすぐるのだ。
仕事柄、何度も部屋を移り住んできた御殿だが、たまに出くわす電気コンロという宿敵にはホトホト泣かされていた。火力も思い通りにならず、挙句の果てにはブレーカー落ちという追い討ちコンボまでご披露してくる。世界の料理スキーには愛されない存在――それが電気コンロ! そう、あの忌々しい電気コンロだ!!
カチッ、ボゥ! カチッ、ボゥ!
コンロを何度も捻っては火力調節、捻っては火力調節。嗚呼、これが感動せずにはいられようか。
「見て狐姫、火力の調節できるのよ。電気コンロでは出来ないはずの素早い火力の調節が出来――」
「そーか良かったな、がんばれよ」
淡々と語る御殿を真顔でガン無視、ソファにゴロンと寝転がってゲームに没頭中。
やれやれ、この感動が分からんとは。御殿は肩をすくめた。
この部屋では火力に泣かされている御殿の姿を見ることはないだろう。たぶん。
リビングのカーテンがきれいに束ねてある。最初から備え付けなのが嬉しいじゃないか。
日光が窓から差し込み、リビングを隅々まで照らしてくれる。
「3階でも絶景ね。遠方まで見わたせる」
数キロ離れたところに山々が連なり、その
まるで老舗旅館の一室から眺めているかのよう。澄んだ風景が御殿に安らぎを与えてくれた。
さほど機械に詳しいわけではないものの、御殿もデジタルネイティブのひとり。システムに頼り切っているせいか、都会の雑踏にまみれていると自然の存在を忘れることがある。
『あなたたち人間は電気やガソリンでは動けない。その
目から摂る栄養は、現代人にいつも何かを訴えかけている。しかし、その緊急性がどれほどのものなのか、今の御殿には想像できなかった。
「狐姫、ここが寝室よ。好きな方を使いなさい」
洋室6畳の別室が2部屋。それぞれに備え付けのシングルベッドが設置されていた。
「おお、ベッドがあるじゃん!」
狐姫は御殿の横をすり抜けるとベッドにダイブ。
「おお~、モッフモフだぜ~、うふふふ……」
ひと部屋は狐姫が占拠した。
ベッドの上でトランポリンのように跳ねたり、枕を抱きながらゴロゴロと仰向けうつ伏せを繰り返している。耳と尻尾をパタパタさせてマッタリ感この上ない。下の階に誰もいないので苦情もない。このマンションは不気味なくらい静かだ。
しばらくの間、この部屋がアジトになる。
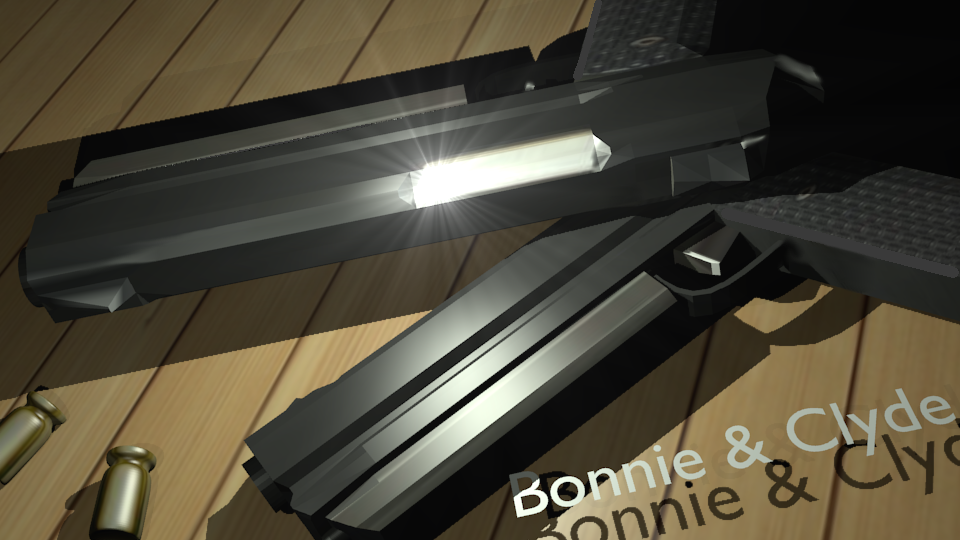
御殿はもう片方の寝室にいた。
持参したトランクをベッドの上に乗せるとダイヤルキーを回してケース開く――中にはドンパチ用の銃器一式がそろっている。この荷物だけは宅配業者に任せるわけにはいかい。
退魔弾はプラスチック製なので一般所持は許されるが、実弾所持は2034年現在でも認可が下りず、銃刀法違反に該当する。アメリカの深刻な治安悪化から銃規制も煽りを利かせ、日本政府も武器所持に対して厳重に取り組んでいる。
御殿は過去にも実弾を運んでいたことがあった。
その時に運悪く職質されたのだが、ポリ公が身体捜査令状を持ってないことを糧に、言葉巧みに逃げきった。
法律はひとつでも多く知っているほうが強い。万が一の時は、ジェラルミンケースで公安の頭をブン殴って逃げるつもりだった。
大切な商売道具、死守すること必死である。
でもね、物騒な世の中よりも平穏がなにより。銃を使わないに越したことはない――と、御殿は常日頃から思っている。
御殿はケースから薬莢の詰まった箱を取り出した。
こちらは実弾ではなく退魔弾。銃にセットしてトリガーを引くと、プラスティック弾が発射される。退魔弾にはサンスクリット文字が刻まれており、術式は悪魔を祓うためのお経のような効果を引き出す。
チベットに『マニ車』というアイテムが存在する――寺院などで僧侶や村人が手にしているお経アイテム。赤ちゃんが使うガラガラ玩具の先端に振り子が付いている形状。筒状の金具に棒が通してあり、筒にはお経がほどこされている。マニ車の筒部分を振り子の遠心力を使って一回しすると、お経を1回唱えた計算になる。
御殿がブッ放す退魔弾もマニ車と同様の原理だ。術式がほどこされたプラスティック弾が発射されることにより、バレルから飛び出た弾丸は回転しながら術を唱えて前進する。螺旋動作を行う弾は、コーンを描きながら音速の波紋を振りまいて一直線に進んでいく。
悪魔を標的としたの場合、退魔術が描かれた弾がヒットすれば、もれなく昇天。弾が描く波紋にかすっただけでも火傷跡のように肌が爛れるので、絶大な効果が期待できる優れものだ。
御殿は退魔弾を2つのマガジンにセットする。その間わずか数秒。コンマ1秒が命取りとなる世界で、リロードを制するものは命を制する。
マガジンはダブルカラム。ずしりと重くなったマガジンから満腹感が伝わってきて、銃口からゲップが聞こえてきそうだ。
銃の使用当初、余計な筋力が入るために照準がブレたりすることもあったが、今はもう慣れたもの。それだけ多くの悪魔を地獄に送り返してきた。
悪魔が憎いほど冷淡になり、引き金を引くときはトドメを刺すことだけを考える。暴魔を相手に躊躇うなど、よほどのことがないかぎりあり得ない。
ガバメントをカスタマイズ化した作りになっており、男の御殿とはいえ細い指先には少々大降りのグリップ。だが上手く使いこなせていた。
二丁それぞれに『ボニー&クライド』という名前がついている。どちらがボニーでクライドかは、御殿のみが知る。
昔、海外のとある武器店に行ったときの出来事だ――仕事がらみで世話になってる同業者から銃を受け取る際、
「ボニーとクライドのように蜂の巣になるなYO、HAHAHA~!」
と、腹がでっぷりと突き出した腕毛ボーボーの店主に笑われながら銃を受け取った。
なにせ相手は英会話オンリー。英語にはまだ不慣れだった御殿は、『これらの銃はボニーとクライドという名前の銃です』と、間違った翻訳をしてしまう。
流暢な英語を話す現在。
手元にある二丁にはボニー&クライドという名前が定着してしまっている。
今のところ名前の修正は考えていないが、外国で起こったド派手な銀行強盗から時間が経った今でも、蜂の巣にされた男女の復讐劇のごとく吠え続けている
ハンドガード直下にはレーザーサイトと高出力フラッシュライトが装備されており、標的のマークや照明ができる。
軍や警察でも採用されているデフォルト仕様。薄さ5ミリの小型チップバッテリーで、点灯を続けても数時間は持つ。長方形構造で軽量化もされており、装着しても重くならない。ミル規格仕様。
※ミル規格とは、米軍で使用できる武器や道具を決める評価基準。試験をパスした武具だけが軍隊で仕様できる。
ボニーとクライド。御殿は2人の男女を両手でクルクルと器用に弄び、腰のガンホルダーに2人を収めた。
「ボニーとクライド、問題なし」
続いて柄状の武器を手に取り、手元にあるスイッチを押す。
シャキン!
硬い物質同士の摩擦が鋭い音を立てた。
柄状の物体の中から勢いよく飛び出した3段もの矛先。柄が一瞬で木刀に変化する。
黒光りする木刀、『
御殿は空泉地星もガンホルダーに挟んだ。
「空泉地星、問題なし」
最後にケースから聖水の入った透明な小瓶を取り出す。
『聖水』――土にまけば悪しき者の侵入を阻止でき、悪魔に直接投げつけることでダメージを与えることもできる。人間の体を清める水でも悪魔から見たら硫酸と同じ。それが身に触れると肌が焼けただれるほどの激痛に襲われる。かつて地獄に足を踏み入れた者が聖水で身を清めて帰還した、などというエピソードまである。万能ウエポン、まさに恵みの水。退魔業者は常備が義務付けられている。
御殿が小瓶を覗きこむ。聖水は窓から差し込む日の光で煌いていた。
「……」
ボ~とする。一瞬の安堵、まどろみ――御殿はこれが好きだった。聖水に嫌悪を見せない自分が今、ここにいる。それは己が悪しき者ではないことの証明になるから。
それでも戦場に身をおく者は皆、同じ穴のムジナだということを認識しなければならない。心を鬼にして挑まなければ、いつか終わりがくるだろう。
『気をつけなさい。闇の深淵を見つめる者は、常に闇の深淵からも見られている――』
どこかの誰かが言った言葉を思い出す。
悪を見つめる者は、同時に悪にも魅入られている。
聖水の癒しは御殿の心がイカレてない証明。そんな確認行動が戦場での習慣になっていた。
「水の女神に感謝します――」
御殿は胸元で聖水を握り締め、目を閉じ、ベッド下の引き出しに道具一式をしまった。
あなたと出会い、そしてはじまる。
学園から御殿の端末に連絡が入った。なんでも街を案内してくれる生徒が来るとのこと。
「なあ御殿~、ハラ減った~」
携帯ゲームに飽きたらしく、枕に顔を埋める狐の猫なで声にクスクスと笑う御殿。時計を見ると、まだ午後3時だ。夕食まで時間がある。
「そうね。食料の買出しにも行くつもりだけど、学園からお客様が来るみたいだからもう少し待ちましょう」
「誰か来るのん?」
「ええ。外で待ち合わせしたから、一緒におやつでも食べに行こうか」
「ホントか!? 俺さ、さっき食べ放題の店見つけたんだよな~!」
耳をピクリとさせて飛び起きる狐姫。そこへ御殿が待ったをかける。
「ダーメ。夕食食べれなくなるでしょ? 買出しから戻ってきたらゴハン作ってあげるから、食べ放題はまた今度」
ご飯食べれなくなるでしょ! 子供からおやつを取り上げる全国の母親よろしく、御殿はつまらなさそうにする狐姫をなだめた。
「俺サマの食欲は無限です」
キリッ。
「家計は有限です」
ピシャリと言い切る母役だった。
部屋を出る2人。
「ほわいとはうす。やっぱ名前負けしてるよな? な?」
負けてると言え! 狐姫が期待した感じで聞いてくる。
「ノーコメント」
「御殿、おまえ宇宙人が怖いんだろ、そうなんだろ!」
あくまで宇宙からの侵略者に攻撃される物件にしたいらしい。
アーチをくぐり、マンションの敷地を出る御殿。
「ここで待ちましょう。それと普段はその耳と尻尾はしまう。OK?」
「うげぇ、めんどくせぇ。まあいいけどさ」
狐姫は壁にもたれかかり、後頭部で腕組をしながら元気な笑みを作る。
「なぁ御殿?」
「ん?」
「学校って楽しいのか? 俺行ったことないんだよね」
まだ見ぬ世界に胸を躍らせているのだろう、無邪気な笑みから未知への期待があふれている。まるで家族にランドセル姿を見せびらかす子供のように――そうやって狐姫の中の冒険心が瞳を輝かせているのだ。と、御殿は思った。
御殿自身、学校生活という思い出があるわけではなかった。やんわりではあるが義務教育を受けた記憶がある……気がする……多分……確かではない。
思い出そうとすると記憶が霧に包まれ、脳内ですっと溶けて消えてしまうのだ。
「学校? そうね……教師と生徒、教室があって、授業があって、部活があって……それから――」
それからはネット辞書に掲載されている内容の重複作業。基本的な学生生活を説明するのがやっとだった。
説明を聞き入る狐姫は、「ふ~ん……」と当たり障りのない返事をしたあと、「そっか、楽しみだな!」と八重歯を見せてニッコリ笑った。
無邪気に笑う相方を前に、一人の人間として知識の力になれない罪悪感が御殿にはあった。記憶の中にある学校に関する知識を片っ端から与えようと試みた。結果、浮かんだキーワードは『友達』だった。
友達という響きは謎が多い。なにをする関係なのか、どこからどこまでを指す関係なのか、始まりと終わりは? 考えると奥が深い。
「友達、たくさんできるといいね――」
そう言いかけた瞬間、御殿の頭に激痛がはしった。側頭部をハンマーで殴られたような振動がする。が、何事もなかったように取りつくろう。
「――てか、そろそろ来る頃じゃね?」
「そのはずだけど……」
マンション前の御殿が細い通りの角を曲がろうとしたまさにその時、ハプニングは起こった。
ドン! ぽよん。
御殿がなにかと正面衝突をしてしまう。というより、御殿の豊満な谷間にのめり込んだ。
「ぶへっ!」
胸になにかがあたりバウンドした。続いて変な音の出るクッションを踏んづけたみたく、素っ頓狂な声がこだまする。
目の前に髪をリボンで結ったポニーテールが尻をさすってヘタレ込んでいる。森からやってきた小動物にも見える。どうやら御殿の胸にバウンドして倒れたようだ。
ひっくりかえった小動物を狐姫が覗き込んだ。
「ん? おい、なんだコイツ! 見てみろよ御殿、パンくわえてるぞ!? いつのアニメキャラだよ、ぶははははっ!」
狐姫が指差し大爆笑。ネット掲示板なら草ボーボー状態。
「むぐ! むぐう~」
棒状のパンを苦しそうにくわえ込むリボンの小動物。
御殿が涙目の小動物の顎に手を添え、パンを抜き取る。
「大丈夫?」
「ぷはっ。だ、大丈夫、でふ」
ひとまず深呼吸の小動物。
御殿の手を取り立ち上がったはよいものの、思っていたよりも力強く引っぱられて足がもつれる。そうして、ふたたび御殿の谷間に顔を突っ込んだ。
「むぐぅ!」
ぽむ……
「2回目かよ、そんなに御殿の胸がお気に入りか?」
狐姫が呆れている。
そこで小動物、にわかオッパイソムリエとして覚醒。
(むむ! ほっぺに吸い付く肌触り。肉まんのようであんまん、大福のようなモッチモチ感。ズシリとしてるクセに軽くてしつこくない)
オッパイソムリエがカッと目を見開いた。
(このおっぱい……事件じゃないの!!! うそ! なにこれ! 胸ってこんなに大きくなるものなの!?)
むぎゅっむぎゅっ。御殿の胸を揉みしだくオッパイソムリエ。
「あ、あの……」
(むううう、実に心地よいバウンド。それに包容感……)
むぎゅ~。
御殿の胸に埋もれたまま、小動物がピタリと動きを止める。
スーハースーハ-くんかくんか。今度は香りを嗅ぎ出した。
「すぅ~。い、いい香り……」
「あ、あの……?」
「Fかな? Gにしては少し小さいかも……」
御殿の胸元の少女が独り言をつぶやいている。が微動だにしない。
そんな奇行でもフリフリ揺れるポニテが子ギツネの尻尾みたいで可愛い。御殿の中で愛着が湧いてくる。
「あ、あの……大丈夫?」
真顔の御殿がポニーテールに声をかけた時、その場に居あわせたヘアパンドの少女と目が合い、思わず顔が引きつる。
(愛宮叶子……)
御殿は自分の目を疑った。目の前にいるのは愛宮のご令嬢、叶子だ。
先日、愛宮邸を訪れた時に拝見したばかりだが、ヘアバンドと鋭い眼光、それにMAMIYA特有の凛として他者の踏み込みを譲らない貫禄が印象的だったのでよく覚えている。グループの黒い噂とは裏腹に、ご令嬢らしい清楚で、慎ましく、整った顔立ちは世間の期待を裏切らないものを備えていた。
叶子は冷静沈着な態度で会釈する。喜怒哀楽をしめさない態度に、御殿は愛宮の気迫に圧倒されていた。
「叶子、さん……」
愛宮様。と、公共の場で呼ばぬよう、宗盛から言われていた。他人を演じていたのでは距離がありすぎるし、だからといって「愛宮様、叶子様」と連呼すれば他の生徒から余計な詮索をされてしまう。警備員としてでなく、あくまで一生徒を演じたほうが学園内では行動しやすい。
それに叶子本人も「愛宮様」を望んでいない。と宗盛から聞かされている。
いつまでもボケッと突っ立っているわけにもいかないので、御殿は口を開いた。
「叶子さん、こちらの方はご友人でしょうか?」
御殿はぎこちないセリフを叶子にぶつけ、胸元の少女をひきはがした。
少女が打ちつけたケツをさすっている。
「叶ちゃんのことご存じなのですか?」
「ええ、理事長と叶子さんは血縁のようですから」
少女の問いに御殿はぎこちない笑みで答えた。役者業もオプション料に含まれる。骨が折れるけど。
狐姫は狐姫で訝しげな表情をポニーテールに向ける。
「どんくせー奴……」
「狐姫」
御殿が狐姫をかるく肘でつつく。
促された狐姫が丁寧な口調で言い直す。
「どんくせー奴、でございまするわね。叶子、いや、叶子さんのご友人は、イテッ」
舌噛んだ。
慣れない丁寧語。話しを合わせるのも骨が折れる。というか日本語まで大変なことになっている。
大根役者は置いといて――。
御殿はポニーテールと向かい合った。
「さっき学園から、案内役が来るっていう連絡があったわ。あなたのことね?」
御殿の目前でポニーテールがビシッと敬礼、転入生に向けて自己紹介をする――
「はい、あたし雪車町想夜です! 要請実行委員会からやってまいりました!」
屈託のない、ひまわりのような明るい笑みで転入生を出迎えた。


